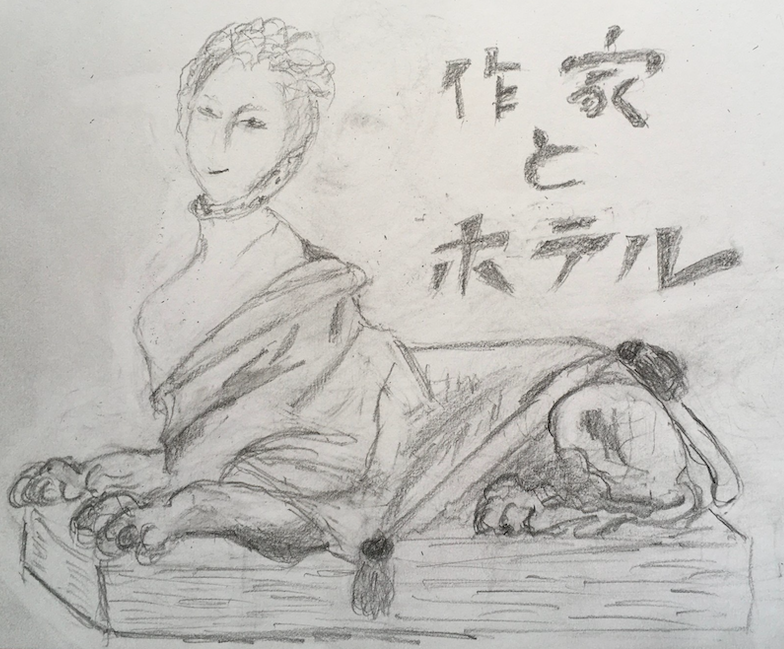
作家がホテルを語るとき、そのホテルが作家を語ります。

池井戸潤
【二人でヒルトン大阪にあるバーに入った。】
『日曜日。半沢は、竹下とともに大阪駅前にあるヒルトン大阪の二階にあるバーにいた。よく半沢が利用するバーだった。店内は広く、椅子の座り心地がいい。隣りのテーブルと適度に離れていて、会話を聞かれる心配もない。酒もうまい。
「どんな調子や、そっちの支店長はんは」
竹下はそういって、意地悪く笑った。
半沢は肩を揺すった。「自業自得。いまにも死にそうですよ。」(中略)
竹下と顔を見合わせてニヤリと笑った。
「債権回収に乾杯や」
差し出されたビールのグラスに、半沢もジンライムのグラスをぶつけた。』
「オレたちバブル入行組」文春文庫より
テレビドラマで大人気となった半沢直樹シリーズの銀行員半沢の決めセリフ「やられたらやり返す、倍返しだ」は、原作では「オレは基本的に性善説だ。相手が善意であり、好意を見せるのであれば、誠心誠意それにこたえる。だが、やられたらやり返す。泣き寝入りはしない。十倍返しだ。そしてーーー潰す。二度とはい上がれないように」。
倍どころか「十倍返し」である。池井戸は元三菱銀行の銀行員だけにモデルに不足はしないのだろう、性根の腐ったどうしようもない銀行員、権力をかさに着て勘違いしている財務省官僚などのワルたちが続々と登場する。
1988 年、バブル時代に就職を迎えた半沢たちの入社面接は「ホテル・パシフィック」で「ホテルの大広間をパーティーションで区切った会場」で行われた。入行間もない新入行員時代には同期と飲むとなると新橋のガード下の縄のれんに行っていた半沢たちも、地方支店の融資課長といった中間管理職クラスになると、ホテルのバーが行きつけになるようだが、大阪では梅田の「ヒルトン大阪」を選ぶところがいかにも銀行員らしい。
「オレたち花のバブル組」では財務の失敗で巨額損失を出した一族経営の独立系老舗ホテルの再建が描かれるが、銀行の内部抗争の材料に使われ、金融庁の担当者の個人的怨念をはらすために使われ、ほとんどの関係者たちが真剣にホテルが生き残る道を考えていないなかで、最後にホテルのオーナーが選んだ再建の道は外資ホテルチェーンと手を組むことだった。
同じく半沢直樹シリーズの「銀翼のイカロス」では日本航空がモデルとなったと思われる破綻する航空会社が描かれているが、破綻そのものを食い物にする再建コンサルタントが記者たちも呼んでの報告会の場所に選ぶのは「内幸町にある一流ホテルの豪勢な会議室である」、とあるがこれは「帝国ホテル」だろう。ワルたちが借景によく使うホテルだ。
いけいど・じゅん●1963生まれ。作家。岐阜県生まれ。慶応大学文学部&法学部卒。1988 年三菱銀行( 現三菱東京UFJ 銀行)に入行、1995 年退職してコンサルタント業、ビジネス書の執筆を行うかたわら江戸川乱歩賞を目指して小説を書き、1998年、「果つる底なき」で江戸川乱歩賞を受賞し作家デビュー。2010 年、「鉄の骨」で吉川英治文学新人賞を受賞。2011 年、「下町ロケット」で直木賞受賞。銀行を舞台にした「オレたちバブル入行組」「銀翼のイカロス」など半沢直樹シリーズはテレビドラマにもなり大人気で、企業エンターテインメント小説とも呼ばれる。中小企業を舞台にした泥臭い人情ものも多い。
池澤夏樹
【人の少ないロビーで少女は一人でその遊びに没頭していた。】
『ホテルにもどったら風呂に入ろうと私は考えた。風呂から出ないままワインを飲もう。それから寝床に移って今日は一日中ずっとうつらうつらして過ごそう。夜になっても部屋から出ず仕事の連絡は電話とメールだけにして夕食はルームサービスで済ませて。そう思ったときになって初めて私は自分がどのくらい疲れているか知った。この数日間の疲れだ。それが雪のように音もなく降って私の心に積もっている。私は冷え切っている。』
新潮文庫「きみのためのバラ」収録の「ヘルシンキ」より
池澤が生まれ、物心つくまで育った北海道帯広市は十勝平野のまんなかにある平原地帯で、まっすぐな道の両側に一面の畑と牧草地が広がり、サイロが建つ、北欧を思わせる景観の土地である。日本ではあるけれど日本ではない、池澤は第二次世界大戦の終戦一ヶ月前の7月、夏とはいえ朝夕は冷えこむ土地で生まれた。短編「ヘルシンキ」の中で池澤がヘルシンキの寒さについて、短い夏について語るとき、それは池澤の体内の記憶に残っている北海道の時間とつながっているのだろうか。「ハワイイ紀行」のあとがきでハワイで体験したサーフィンのことを「波に乗った喜びは生理のレベルで記憶している」と書いている人だから。「ヘルシンキ」では、そこで描かれているホテルの名前はない。しかし、川に近く、凍った川でスケートができる、と描かれていることから、おそらく「ヒルトン・ヘルシンキ・ストランド」ではないかと思われる。冬の厳寒の北欧を舞台にしたこの作品には、ロシア人と国際結婚したものの離婚した日本人男性のホテルゲストとそのハーフの幼い娘との交流が描かれている。
同じ短編集「きみのためのバラ」に収録されている「都市生活」にはこんなシーンがある。ホテルのチェックインの際にレセプショニストが「クレジット・カードを掲示して、回線で認証も下りたはずなのに、ホテル側は金額を書き入れていないクレジット伝票にサインしろという。」これに対して主人公は、「ブランクの伝票にはサインしません」と突っぱねる。
そして、「それはどんな場合でもしてはならないことだし、客に求めてはいけないことです」と主張する。これはおそらく池澤の実体験だと思われるが、世界各地を旅して来た人であることがよくわかる。池澤は放浪の人でもある。ギリシャに3年間移住し、その後も沖縄、フランスのフォンテヌブロー、札幌市と移り住んでいる。フランスから帰国後「同じ空気の中に住みたいと思って、札幌に決めた。ここの今日の湿度は六八パーセント。やっぱり乾いている。」。
生まれた土地の空気感がやはり落ち着くのだろうか。
いけざわ・なつき●1945 生まれ。作家、詩人、翻訳家。北海道帯広市で、作家の福永武彦と詩人の原條あき子との間に生まれる。両親が離婚後、母と共に上京。都立富士高校卒業後、1964 年に埼玉大学理工学部物理学科に入学。1968 年に大学を中退した後、しばらく翻訳の仕事で身を立て、1975 年にギリシアに移住、3 年間を過ごす。小説「スティル・ライフ」で、1988 年に芥川賞受賞した後、1993 年に沖縄に移住。2005 年にフランスのフォンテヌブローに移住。2009 年に北海道札幌市に移住。小説「マシアス・ギリの失脚」で谷崎潤一郎賞、「花を運ぶ妹」で毎日出版文化賞。随筆「母なる自然のおっぱい」で読売文学賞。「ハワイイ紀行」で JTB 出版文化賞。
伊集院静
【冬の海辺のホテルは宿泊客もなく静かであった。】
『私はここでホテルが客に何を提供するのかを学んだ。それは、ゲストの人生のひとときをいかに快適に過ごしてもらうか、という哲学である。ゲストが必ずしも愉しむだけのためにホテルを訪れていない時もある。悩みを抱えた人、哀しみ、追憶の日々を送っている人、さまざまな人生模様を、品格を持って静かに迎えることもホテルの大切な役割である。』
小学館「なぎさホテル」より
ずいぶん前のことだが、「文化人のホテル」として知られていた駿河台の「山の上ホテル」のバックヤードのボードに「伊集院静先生」という滞在中のリクエストを書いたメモが貼ってあり、その書かれた内容を見て、この人、かなりホテルを使い慣れているな、と思ったことがある。後に、「逗子なぎさホテル」に7年あまり住んでいたことがあると知った。
今はもうないこの伝説のホテルは、昭和元年に開業し、昭和が終わった年にクローズした。かつては外国人客が多く訪れ、皇族が葉山の御用邸滞在時にはぶらりと食事にやってくるようなホテルであった。有名作家になってからホテル住まいをした作家は多いが、伊集院の場合、作家になる気も、もっといえば何になる気もなく、離婚による借金を抱えてお先真っ暗、定職もなく懐には宿泊費を払う金もないにもかかわらず、海辺で見かけた伊集院をひと目で気に入ったらしいGM(総支配人)の並はずれた好意により、このホテルの「客」となった。そんなまだ何者でもなかった時代の伊集院に対して、素朴に接する現場のスタッフたちとの交流シーンの描写がこのホテルの本質を語っている。
本書で伊集院は自分の出自について、さらりとさらけ出しているが、意味もなく下に見られたり馬鹿にされたりするのには我慢がならない性分のようで、理由もなく人を小馬鹿にしたり威張り散らしている人々への嫌悪感は激しい。本書でも「中でも私が嫌悪したのは、自分たちが上流階級に生きていると思っている人たち」。だから、なぎさホテルにおいても、そうした優越意識を持つ常連客へのまなざしは厳しい。「どのホテルでもそうだが、常連客はどこか我儘になるし、特権意識を持つ人が多い。…中略…あきらかに奇異なものを見る目で、彼らは私を観察していた」。
伊集院にとって、なぎさホテルとは、わずか1年にも満たない結婚生活を鎌倉で過ごした後、不治の病で逝ってしまった夏目雅子との結婚前の逢瀬の場でもあった。おそらくホテルと夏目雅子の思い出とは一体だろう。本書「なぎさホテル」とは、亡き前妻、夏目雅子への鎮魂歌なのかもしれない。
いじゅういん・しずか●1950年生まれ。作家。山口県防府市生まれ。在日韓国人二世で後に帰化。立教大学文学部日本文学科卒。広告代理店電通勤務の会社員生活を経た後、CM ディレクター、コンサート演出などをしながら執筆活動を始める。1981 年「皐月」でデビュー。1990 年「乳房」で吉川英治文学新人賞受賞。1992 年「受け月」で直木賞受賞。1994 年「機関車先生」で柴田錬三郎賞受賞。2002年「ごろごろ」で吉川英治文学賞受賞。最近では「大人の流儀」「無頼のススメ」「大人の男の遊び方」など、エッセイも多い。伊達歩のペンネームで作詞家としても日本レコード大賞を受賞した近藤真彦の「愚か者」「ギンギラギンにさりげなく」などのヒット曲を持つ。
カズオ・イシグロ
【すでに夜になり、私はこの居心地のよい宿に落ち着いております】
『どちらかといえば質素と言える建物でしょうが、清潔で、私が一泊するにはなんの不都合もありません。宿の主人は見たところ四十前後の女で、なにやら私をたいそうな客とみなしているふうですが、これはファラード様のフォードと、私の上等のスーツに影響されてのことに違いありますまい。(中略)宿帳の住所欄に「ダーリントン・ホール」と記しますと、女主人が少し慌てた顔つきでこちらを見ましたが、あれは、私をリッツやドーチェスターに泊り慣れた紳士だと勝手に思い込んだための狼狽でしょう。』
ハヤカワepi 文庫「日の名残り」より
ノーベル文学賞を受賞した日系イギリス人作家である。英国でブッカー賞を受賞した代表作の「日の名残り」は、英国人執事が主人公の物語だが、伝統的な英国執事の鑑のようで「品格そのもののような人であった」と誇りに思う父を持ち、自分も執事であることに誇りを持つ「品格ある」執事である、いや、そうありたいの願う彼、スティーブンスの視点で物語は進行する。
スティーブンスが、仕事ができて、かつ「品格ある執事とは」と考える理想の執事の存在の仕方、「職業的あり方」、持つべき能力、仕事ぶりは、ホテルジャンキーにとっては、まさに理想のホテルマンの姿のようである。彼は言う、「執事はイギリスにしかおらず、ほかの国にいるのは、名称はどうであれ単なる召使いだ、とはよく言われることです。私もそのとおりだと思います。」。そして、「偉大な執事は、紳士がスーツを着るように執事職を身にまとい(中略)それを脱ぐのは、みずから脱ごうと思ったとき以外にはなく、それは自分が完全にひとりの時に限られます」。
これはまさにホテルのGM(総支配人)の資質である。
上の引用文は彼が英国を車で旅行した際の宿泊先ホテルについて書かれたものだが、「ソールズベリー市の中心からさほど遠くない」としか書かれていないが、おそらくこんなホテルだったのではあるまいかと筆者が想像したのが、「ザ・スワン・イン・アット・ストフォード」である。この作品はほとんどが旅先でのことなのだが、ホテルについての記述は少ない。最後の方で登場するのがリトル・コンプトンの「ローズガーデン・ホテル」で、元同僚の女性とこのホテルの喫茶室で会うシーンがある。その喫茶室については「そこは、雑多な肘掛け椅子の間にいくつかのテーブルを配置した部屋になっておりまして」としか描写されていない。あとは、出窓から「雨に煙る村の広場」が見えるらしいことだけで、「灰色の光の中で」二人は二時間ほどおしゃべりを続ける。ホテルはあくまでもモノトーンの背景だ。イシグロがホテルを舞台に小説を書くとするとどんな作品になるのだろうか。
カズオ・イシグロ●1954年生まれ。作家。日本人の両親のもと、長崎県長崎市に生まれ、5才の時に海洋学者である父親の仕事のため一家で渡英しサリー州・ギルドフォードに移住。1983年英国に帰化。1978 年にケント大学英文学科、1980 年にイースト・アングリア大学大学院創作学科に進み、小説を書き始めた。卒業後ミュージシャンを目指したが、1982 年「女たちの遠い夏」で王立文学協会賞を受賞。1989 年「日の名残り」でブッカー賞受賞。2000 年に「わたしたちが孤児だったころ」、2005 年に「わたしを離さないで」を出し、世界的なベストセラーになる。2017 年ノーベル文学賞受賞。
内館牧子
【テラスの向こう、海は刻々と暮れ色を深めている。】
『ホテル銀波には久しぶりに来たが、やはりいい。相模湾を一望できる高台に建ち、ヨーロッパの古いホテルのような、小さく格式がある名門だ。現役時代には会合やゴルフなどでよく使ったが、定年後は思い出すこともない無縁のホテルになっていた。
俺はいつも利用していた部屋より二ランク上をおさえた。
ダブルがよかったが、ツインにした。久里が部屋に入って来た時、ダブルではあまりに下心が見えすぎる。(中略)もうじき、この部屋に久里が来る。そして泊まる。それを思うと、他のことが頭に入らない。』
講談社「終わった人」より
内館は、世の中でみんなが心のどこかでなんとなく感じている本音の世界、時代の気分をすくいあげながら、テレビドラマ化し、次々にヒット作を世に送ってきたドラマの脚本家であるが、同時に小説の名手でもある。美大を卒業した後、13 年半にわたってOL 生活を送った。三菱系のお堅い会社での事務職だったが、腰掛け気分ではなく、ちゃんと仕事をしたそうだ。このOL 生活を通じて日々、肌で感じたサラリーマン世界は、後に彼女が脚本家となった時に生きてくる。そして脚本家を夢見て毎日1本の映画を見ることを自らに課し、それを実行したというあたりが並ではない。
最新刊でベストセラーの「終わった人」でも会社員人生の” ああ無情” と悲哀、そして男たちの純情ゆえの喜劇を描いている。大手銀行でエリート行員だった主人公の田代は、取締役一歩手前で出世コースからはずれ、49才で子会社に出向、51 才でだめ押しの転籍をさせられ、63 才で定年を迎えた。年収1,300 万円のサラリーマン生活が終わり、その時点で、保有資産は約1億5千万円。別に妻名義のマンションと美容院もある。はたから見れば、老後は楽勝の勝ち組であろう。しかし、だからといって幸福にはなれないのが、人間である、というより、男である。ここから田代がたどるのは「終わった人」であることを自分で認めるために、多くの人々がたどるお決まりのコースである。東大法学部卒の彼の場合、世間体もプライドも許す学問の道をめざす。その準備を理由にまずカルチャーセンターへ。そして、フィットネスジムへ。しかし、これらの場所はすべて今や「終わった人」たちの溜まり場と化していたのだった。「終わってない男」である証明の若い女性との” 恋” に心浮き立つのだが、その舞台として登場するのが、会社員時代行きつけだった「ローストビーフがうまい」東京會舘、西麻布のイタリアン「アルポルト」。下心満々で誘う熱海のホテルは、かつて接待でよく使った「ホテル銀波」とあるが、おそらく旧「蓬莱」(現 星野リゾート 界 熱海)系の「ヴィラ・デル・ソル」(現 界 熱海 別館ヴィラ・デル・ソル)をモデルにしたものだろう。
うちだて・まきこ●1948年、秋田生まれ。作家、脚本家、作詞家。武蔵野美術大学造形学部基礎デザイン学科卒業後、三菱重工業に入社。13 年半のOL 生活を経て1988 年脚本家デビュー。主なテレビドラマの脚本にNHK 連続テレビ小説「ひらり」、読売テレビの「寝たふりしてる男たち」、NHK 大河ドラマ「毛利元就」、TBS「年下の男』など。主な著書に「エイジハラスメント」「終わった人」など。
宇野千代
【私たちは結婚式を挙げることになった。会場は帝国ホテル】
『昭和16 年の四月であった。私と北原とは満州や中国に長期の旅行を試みた。ハルピンに滞在中、あれはキタイスカヤ・ホテルと言う、ハルピン第一の大ホテルであったが、旧ロシア風の建築で、顔を洗うときにも、壁に嵌め込んである大きな鏡や洗面器に私たちの背丈が届かず、背伸びをしてもまだ届かないので困ったものであった。しかし、夜食のとき、私たちのことを、日本から来た著名な作家とでも言うのか、私たちの席に、バイオリン弾きの男が近づいて来たではないか。』
角川文庫「生きていく私」より
尾崎士郎、久米正雄、芥川龍之介、今東光、梶井基次郎、三好達治、川端康成、小林秀雄、青山二郎 ….. 日本文学全集でも編めば常連さんとして欠かせない作家や評論家たちが並んでいるが、彼らは全員、宇野千代が親しく「親交」を結んだ男たちである。川端康成の場合は、同じ布団には寝たけれど、お互い中性的な関係だったなどと著書「生きていく私」の中で書いているが、さて、どうだったのだろうか。
尾崎士郎とは結婚して離婚したが、尾崎を捨てて移った相手は画家の東郷青児。とにかく強烈な女なのである。「じっと目を見つめれば男は落とせる」などとうそぶいていたらしいが、あっという間にズカズカと、時にするりと、気がつけば男の横で体を寄せている、という、いかにも “魔性の女” 風に自分を演出していた女性、それが宇野千代という作家である。
彼女の本性について見抜いていたのは、東郷青児だ。「君はこの小説(東郷青児の話をモデルにした代表作の「色ざんげ」)を書くために僕と一緒になったのだろう」と看破している。
こうしたことから、小説よりも華やかな男性関係について話題にされる宇野千代だが、彼女は事業家でもあり、時代の先端をいくファッション雑誌「スタイル」を創刊したり、着物のデザインビジネスをやったりし、会社が倒産したりもして浮き沈みは大きいけれど、豊かに暮らした時期も多かった。
そんな彼女が、4 番目で最後の夫である北原武雄と1939年(昭和14年)に結婚式をあげたのは「帝国ホテル」で、媒酌人は、女流作家として当時は人気があった吉屋信子と画科の藤田嗣治。その後、傘寿のお祝いパーティーなど、「帝国ホテル」は折々の機会に利用していた。ちなみに最後の夫、北原とも1964年(昭和39年)に離婚した。1951年(昭和26年)、スタイル社の経営も順調だった頃にフランス旅行をしているのだが、この時、彼女がパリで泊まったホテルはどこだったのだろうか?
うの・ちよ●1897 〜1996。山口県岩国市生まれ。岩国高等女学校(現 山口県立岩国高等学校)卒。1921年「時事新報」の懸賞短編小説に「脂粉の顔」で応募し当選、作家としてデビュー。1936 年にファッション雑誌「スタイル」を創刊。代表作に「おはん」「色ざんげ」「生きて行く私」など。長寿で98 歳の最後まで元気な様子をエッセイに綴り、「私何だか死なないような気がするんですよ」という作品となった。
角田光代
【窓の外を見るのに飽きて、左織はベッドに横たわる。】
『ホテルは大きな駅の近くにあった。入り口にドアマンのいる立派なホテルで、部屋も広く清潔だ。左織は窓に近づき、レースのカーテン越しに外を見る。正面には同じような高さの建物があり、見下ろすと、車道と、歩道を歩く人の姿が見える。建物のせいで道路も歩道も日陰になっている。
ニューヨーク旅行は風美子が計画を立てた。 …中略… そうね、と相づちは打っていたものの、どうも一家揃って外国に行くという現実味はまるで持てなかった。
けれど今、ニューヨークにいる。』
新潮文庫「笹の舟で海をわたる」より
旅好きで知られる作家で、「世界中で迷子になって」(小学館文庫)、「降り積もる光の粒」(文春文庫)など旅もののエッセイ集の人気も高い。が、これらのエッセイにホテルが名前付きで登場することはほとんどない。元バックパッカーで、何か目的があって旅するというよりぶらぶら放浪派なので、泊まる宿もホテルそのものに惹かれてということはないように見受けられる。
宮沢りえ主演で映画化もされた「紙の月」(ハルキ文庫)には、「赤坂にあるホテル」という表記で不倫のカップルがスイートに10日間泊まるシーンが出てくる。「鉄板焼き屋でコース料理を食べ」とあるのを読むと、「ニューオータニ東京」だろうと思われるが、スイートでの過ごし方の描写はホテルライフが好きな人のそれではない。この作品で、唯一、実名でホテルが出てくるのは、年下の恋人との逢瀬の場所として「渋谷で泊まったアリマックスホテルのような、こぢんまりしたホテル」の箇所。このホテルを知る人にだけわかるもの、主人公の人妻が求める時間がどんなものなのか、ここに込められている。
「笹の舟で海をわたる」(新潮文庫)から抜粋した上のニューヨーク旅行のシーンに出てくる「大きな駅」とは、おそらくグランドセントラル・ステーションのことだろう。だとすると、この駅のすぐ近くにあるホテルとは、時代からいって1976 年に開業した「グランドハイアット・ニューヨーク」ではなかろうか。売れっ子で高収入の料理研究家の女友だちが手配したホテルだから、多分そう悪くないグレイドのところだろう。午後のシーンで建物のせいで歩道も道路も日陰になっているということは、南北に走るレキシントン・アベニューの西側だ。今では部屋が狭いと言われるこのホテルでも、バブル前の日本人にとっては広く感じたのかもしれない…などそんな当時の時代感覚も感じさせる描写だ。
彼女がホテルそのものに焦点を当てて書くときはどんな書き方をするのだろうか? それをぜひ読んで見たいと思う作家だ。
かくた・みつよ●1967年、横浜市生まれ。早稲田大学第一文学部文芸専修卒。もともと作家志望だった。1988 年、大学在学中、彩河杏のペンネームで書いた「お子様ランチ・ロックソース」でジュニア小説のコバルト・ノベル大賞受賞。1990 年、角田光代として書いた「幸福な遊戯」で海燕新人文学賞受賞。2005 年、「対岸の彼女」で直木賞受賞。2007 年 、「八日目の蝉」で中央公論文芸賞受賞。2012 年、「紙の月」で柴田錬三郎賞受賞。
兼高かおる
【ホテルで満足したのはクリヨンとリッツです。】
『食事もさることながら、サーヴィスの仕種が何ともきれいなのです。立ち方、腕の伸ばし方、間の取り方が一流のプロを感じさせるのです。チップに100 ドル(撮影をしたので彼にいろいろ面倒かけたからです)を渡すと、その受け取り方も一流でした。感謝の表情を浮かべ、直立して首をかしげ、「メルシー・マダム」と心の底からのようにお礼を言う。実に上手なのです。渡した私の方が気分が良くなってしまいました。』
新潮文庫「「私の好きな世界の街」より
作家といっても、文学者ではない。ジャーナリストであり旅行作家である。そして、物を書くというより、「語る」人であり、兼高かおるという「存在」そのものである。旅に関する著書も、読んでいるとあの声で語られているような気になる。30 年間というテレビ界でも有数の長寿番組だった「兼高かおる世界の旅」では、聞き手の芥川隆行を相手にオッホッホッホと闊達で朗らかに笑い転げ、「わたくし…ですのよ」と品よくきちんとした言葉遣いながらもぽんぽんと歯切れよく語る独特の語り口と、イギリスのチャールズ皇太子(当時)であろうと、サルバドール・ダリであろうと、相手が誰であろうと、物おじせず自然体でやりとりする様子に、海外旅行がまだ今ほど一般的でなかった時代、日本の人々は驚きと憧れをもって見入ったものだった。
ホテルの使い方については、さすがによく知っている。サンフランシスコでは街を散歩し「こうして歩き疲れたころ、ケーブルカーでノブ・ヒルに上り、「フェアモント・ホテル」に寄ってアフタヌーン・ティーをとり、家に戻ります。シャワーを浴びて一休みして、空が赤く染まり始めたらちょっといいドレスに着替えて、夕暮れの一杯に出かけるのです。行く先はこれも歩いて行ける「マーク・ホプキンズ・ホテル」。十九階のトップ・オブ・ザ・マークのウェイターに慇懃に迎えられながら窓際に席を取り、街に灯がちらちら瞬く景色を眼下に、カクテルを味わいます」(新潮文庫「私の好きな世界の街」より抜粋、以下同様)といった具合だ。また、パリの「クリヨン」では、古い友人(これが元ケネディ大統領の秘書官夫妻)を「個室をとってランチにお招きしました」。ロンドンでは「朝食は、かつての定宿だったドーチェスター・ホテルの朝食がもっともお気に入りでした」。こんなふうに名門ホテルを利用する一方で、スイスのバーゼルでは取材の際に駅に近くて荷物を運ぶのに便利だと言って「私の定宿は中央駅前のヴィクトリア・ホテル」とも。ホテルをよく知りぬいて、自分のものにして使いこなしているようすがうかがえる。
かねたか・かおる●1928 〜2019年。兵庫県神戸市生まれ。ジャーナリスト、旅行作家。日本旅行作家協会元会長。香蘭女学校卒業。1958 年 、スカンジナビア航空主催の「世界早回り」で73時間9分35 秒の新記録を樹立。1959〜1990 年、TBS のテレビ番組「兼高かおる世界の旅」のレポーター、ナレーター、プロデューサー兼ディレクターを務める。主な著書に「兼高かおる 旅のアルバム」「私の愛する憩いの地」「私の好きな世界の街」「わたくしが旅から学んだこと 80 過ぎても「世界の旅」は継続中ですのよ!」など。
桐島洋子
【最後の1 日だけ、豪奢な夢を見るのもいいだろう。】
『日常生活に溢れるものや喧騒をそぎおとし、快適に住むためだけの要素だけ簡潔にしたホテル。ホテルの部屋に入ってドアを閉めると 結界の中にいるような深い安堵感に包まれる。たまに気合いを入れてホテルに贅沢するのはたぶん無駄にはならないだろう。いま流行りのリセットには転地や旅行がお勧めだが、近場のホテルでとりあえずワープしてみるのも悪くない。』
「聡明な女たちへ」(大和書房)より
半世紀前、まだシングルマザーが珍しかった時代に女手ひとつで三人の子どもを育ててきたことにスポットライトが当たることが多いが、1971 年に刊行され大宅壮一ノンフィクション賞を受賞したルポルタージュ「淋しいアメリカ人」は、現代アメリカ社会の病んだ深層をえぐる評論として高い評価を得た。また、ベトナム戦争時代には、なりゆきではあったが従軍記者となり、ジャーナリストとして戦争報道も行った。
1976 年に出版されベストセラーになった「聡明な女は料理がうまい」をはじめ、自立した女性としての生き方についてのエッセイを多く世に出してきたが、世界各国を旅した豊富な経験から、いろいろなホテルの「使い方」を編み出してきた人でもある。
三人の子どもの子育てをしていた時代、夏休みに子どもたちの預け先がみつからないと、勤め先の文藝春秋社の近くにあるホテルのプールで子どもたちを日中遊ばせ、ときどき様子を見に行っていたという。また、仕事が忙しいときには「ちょっと奥まってるホテルでね。安心だったのよ」と、ホテルのロビーに子どもたちを「放牧して」いたこともある。
ホテルジャンキーとして非常に印象的だったホテルの使い方は、若い時からバックパッカー旅行であっても、最後の一日だけは、それまでの安宿から一転し、その街で最高級のホテルの、それもスイートに泊まる、というもの。チェックインするときはジーンズにT シャツ姿だが、ディナーの際にはきちんとドレスに着替え、ダイニングルームで優雅にゆっくり食事を愉しむという。なかなかのホテルの使い手であり、楽しみ方の術を知っているとお見受けする。
「聡明な女たちへ」は70 代のはじめに出版したエッセイだが、80 代になった年に出した「いくつになっても、旅する人は美しい」でも「年齢を重ねるほど、実りの多い充実した時間を過ごせるようになるのが旅」、「懐かしい場所を再訪したり、一期一会の出会いにワクワクしたり。思わぬハプニングも楽しんで!」とシニアたちに向けてメッセージを送っている。
きりしま・ようこ● 1937 年東京生まれ。神奈川県葉山で育つ。都立駒場高校卒業後、文藝春秋社に勤務。退社後に書いた「淋しいアメリカ人」で大宅壮一ノンフィクション賞受賞。
ベトナム戦争時代には従軍記者として活動。主な著書に「聡明な女は料理がうまい」、「マ
ザー・グースと三匹の子豚たち」など。
近藤紘一
【私は泳ぎつかれるとその熱帯樹の茂みを散策する。】
『郊外にパタヤという海岸がある。(中略)フランス人が見つけて開発し、そのご、ベトナム帰休の米兵たちがつめかけて目茶苦茶にしてしまった保養地で、日本でいえばさしずめ片瀬、由比ヶ浜か。
海岸のはずれに一軒だけフランス人マネージャーが残っているホテルがある。私たちはいつもそこのプールを使う。なぜかこのホテルだけ、米人、日本人の観光客が少ない。客の多くはバンコクから来るフランス人、ドイツ人、それにタイ人などである。』
文春文庫「バンコクの妻と娘」より
東南アジアを専門とする新聞記者で、ジャーナリストとしての高い評価を得た仕事も多くしたが、ベトナム人の妻と娘(妻の連れ子)について書いたエッセイのシリーズが人気だった。
特定のホテルについて自分の思いを書くことは少なかったが、海外特派員生活が長く仕事柄ホテル経験は豊富だった。サイゴン陥落の際には作家の開高健も当時泊まっていた「ホテル・マジェスティック・サイゴン」に住んでいたこともある。社命により短期で本の執筆をしなければならなかった時は、かつて九段下の千鳥ヶ淵にあったこじんまりした「フェアモントホテル」でカンヅメになった。バンコクでは自宅のアパートの近くにある「この土地にしてはめずらしく落ち着いた作りで、純白のマキシの裾に明るいグリーンの線をあしらったウェイトレスらのコスチュームも優雅で色気があった」というホテルのラウンジに妻が留守の晩にリセ(フランス人学校)に通っている娘とふたりでお茶を飲みに行ったりしている。そこには娘が憧れる美人のウェイトレスの女性がいて、父娘との交流が生まれる。
こうしたそれぞれのホテルとのつきあい方を見ていると、近藤は「ホテル柄」を熟知したうえで、あたかも人づきあいと同じように、それぞれのホテルと上手なつきあい方をした人だと思う。「バンコクの妻と娘」や「パリに行った妻と娘」などに登場する、タイのパタヤビーチの「オーキッド・ロッジ」は、宮仕えの身でもまかなえるくらい値段も手頃だったとはいうものの、普通のクラスのフランス人たちがヴァカンスの際に家族で長期滞在するようなホテル。近藤だからこそ選んだホテルだと思う。本が書かれた1970年代後半の当時、バンコク駐在員の日本人たちは、もっと別のホテルを選んだであろう。
二度の結婚(一度目の妻は日本人外交官の娘)をしているが、二人の妻はまったく逆のタイプで、それぞれの妻とのつきあい方も、本人の書くところによるとまったく異なるようだ。近藤にとっては人もホテルも等距離の存在だったのかもしれない。小説家の眼をもったジャーナリストだった。
こんどう・こういち●1940 〜1986年。作家、ジャーナリスト。東京生まれ。神奈川県逗子市で育つ。早稲田大学第一文学部仏文科を首席で卒業。サンケイ新聞(現・産経新聞)入社。1967 年〜1969年フランス留学。1971 年〜1974 年、サイゴン支局長。1975 年、臨時特派員としてサイゴン陥落を経験。1979 年、大宅壮一ノンフィクション賞受賞。1980 年、 ボーン・上田記念国際記者賞受賞。1984 年、小説「仏陀を買う」で中央公論新人賞受賞。主な著書に「サイゴンから来た妻と娘」「パリに行った妻と娘」「したたかな敗者たち」「目撃者たち」など。
佐藤 優
【小さいけれど外交官が好んで使う高級ホテルだ。】
『フロント係が「みなさんの場合、外交官割引が適用されて1泊80ポンドになります」と説明しているのが聞こえた。1泊2万円ならばなんとかなる。それにしても、こんなに安くなるとはすごい特権を外交官は持っている。
部屋はそれほど広くない。30平方メートルに少し欠けるくらいだ。天井は高く、アンティークの家具が入っている。モスクワのホテル「ウクライナ」のベッドは小さく、布団から酸っぱい臭いがした。このホテルのベッドはセミダブルで、布団からも変な臭いはしない。』
新潮文庫「紳士協定:私のイギリス物語」より
この人を見ていると、つくづく人生なにが幸いするのかわからないものだと思う。ロシア語を専門とするノンキャリアの外交官としてスタートし、その当時自分が思い描いていたその後の人生とは「モスクワの日本大使館、レニングラードかナホトカの日本総領事館と東京の外務本省を往復することになると思う」(新潮社文庫「紳士協定」より、以下同様)。ライフワークと考えていた神学の博士論文を書くため「誰もここで働きたいと思わない」ナホトカで、「勤務の延長を願い出ようと思っている」。
しかし、人生、巡り合わせというものがある。東西冷戦下で東社会の盟主だったソ連邦の解体、これまでの世界の枠組みが崩壊するという激流のような時代の流れは、佐藤の人生をも大きく変えることになった。
後に佐藤が鈴木宗男事件に連座して逮捕され、513日の独房での獄中暮らしをするようになった原因は、佐藤が外交官として抜群に仕事が出来たことによる。ソ連邦の解体プロセスにおいて、佐藤が彼の地で築き上げてきた幅広く深い人脈は貴重な情報源となった。キャリア外交官たちが触れることもできない中枢の重要人物にまで食い込み、人間と人間としての深い信頼関係を結び、腹を割って話せた。1991年の在ロシア日本国大使館に勤務時に起きたクーデタ時にはアメリカよりも早くゴルバチョフの生存情報を確認したという。しかし、組織社会では、こうした突出した有能さは諸刃の剣である。使える時はいいように使われるが、局面が変わり、組織にとってその存在が邪魔になるときはまっさきに切り捨てられる宿命を背負っている。
あの事件のおかげで、佐藤は「刑事事件で禁固以上の刑が確定したために、自動的に国家公務員の身分を失った」ことにより、作家活動に入った。佐藤は言う。「職業作家になってから、取り憑かれたように文を綴っている。書きたいことがあるからだ」。もし、あのまま外務省でていよく使われていたとしたら、いま佐藤が奔流のように書いている作品群を私たちは読むことができなかった。
さとう・まさる●1960年、東京生まれ。作家。元外交官。東京都出身。埼玉県大宮市(現さいたま市)育つ。浦和高校在学中、ひとりで東欧を旅行。同志社大学神学部卒。神学修士。チェコ留学を目論んで、1985年ノンキャリアの専門職員として外務省入省。在ロシア大使館三等書記官、外務省国際情報局分析第一課主任分析官などを歴任。2002年、鈴木宗男事件に連座して逮捕され、有罪判決を受ける。ロシア語通訳の米原万里氏葬儀では弔辞を読んだ。主な著書に「罠」「国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて」「獄中記」など。
志賀直哉
【ぼんやりと部屋の前の椅子に腰掛けて】
『自分の部屋は二階で、隣のない、割に静かな座敷だった。読み書きに疲れるとよく縁の椅子に出た。脇が玄関の屋根で、それが家へ接続する所が羽目になっている。その羽目の中に蜂の巣があるらしい。虎斑の大きな肥った蜂が天気さえよければ、朝から暮近くまで毎日忙しそうに働いていた。(中略)
自分は退屈すると、よく欄干から蜂の出入りを眺めていた。(中略)
夜の間にひどい雨が降った。朝は晴れ、木の葉も地面も屋根も綺麗に洗われていた。』
新潮文庫「城の崎にて」より
「小説の神様」と呼ばれた文豪だけに、ちょっとでも足跡を残した旅館ではその亡き後も語り継がれることになる。
そのひとつが、兵庫県城崎温泉の創業300 年の老舗「三木屋」。志賀が「城の崎にて」を執筆したところとして知られ、作品の舞台にもなっている。執筆時には3 週間ほど逗留したそうで、上の引用文で描写されている庭園に面した2階の部屋とは、特に気に入っていた26 号室。ここの庭園は「暗夜行路」にも登場する。三木屋は志賀の定宿のひとつとなり、以後、十数回に渡って再訪を重ねている。
「豊年虫」は信州の戸倉温泉「笹屋ホテル」逗留中に執筆されたと言われている。
「書簡」が書かれたのはかつて蒲郡にあった料理旅館「常盤館」だが、ここの洋風別館としてスタートしたのが「蒲郡クラシックホテル」である。
雑誌「白樺」の創刊は、東京帝国大学在学中の1907 年10 月、学習院の友人・武者小路実篤と旅館で泊りがけで話し合ったのがきっかけだと言われているが、その旅館とは、神奈川県藤沢市の鵠沼海岸にかつてあった料理旅館「東屋」。志賀の短編「鵠沼行」には「東家」として書かれているが、庭には中の島もある大きな池があり舟遊びもできたビーチリゾートホテルだった。
1952 年に柳宗悦、濱田庄司、梅原龍三郎ら学習院&白樺派の親しい友人たちとヨーロッパ周遊旅行をしているのだが、この時のホテルがわからない。旅先ではいつも最高級ホテルのスイートルームに長期滞在して絵を描いていたという梅原が一緒なので良いホテルだと思うのだが。
学習院の親しい友人のひとりでスイスでホテル経営を学んだ岩下家一は逗子の「なぎさホテル」の創業者だが、岩下に頼まれ志賀の父が資金を貸した。
志賀は引越魔として知られ生涯で23 回引越しを繰り返したが、自ら自邸や友人宅の設計を手がけ建築・インテリア好きでもあった。もし志賀がホテルを手がけていたら、どんなホテルだっただろうか。
しが・なおや●1883 〜1971年。小説家。父親の赴任先の宮城県牡鹿郡石巻町で生まれ、2才より東京で育つ。大きな影響を受けたと言われる祖父・直道は相馬家の家令。小中高と学習院に通い、1906 年東京帝国大学英文学科に入学するも夏目漱石の講義以外は興味が持てず1910年中退。同年、同人誌「白樺派」を学習院時代の友人である武者小路実篤、有島武郎、里見弴、柳宗悦らと共に創刊。明治時代の財界の重鎮として知られる父・直温との不和と和解が小説のテーマと言われている。主な作品に「城の崎にて」「小僧の神様」「和解」「暗夜行路」など。
島田雅彦
【横浜のホテル・ニューグランドに車を寄せると、フロントで部屋の鍵を受け取り】
『映画が終わると、私たちは帝国ホテルのコーヒーショップに行き、そこで遅いランチを取りました。
(中略)
私の希望に応じ、花岡は高校進学祝にワンピースを買ってくれ、銀座のステーキハウスに連れて行ってくれました。口に入れると、とろける極上の霜降り肉ステーキの脂と肉汁に、私はすっかり酩酊してしまいました。こっそりと口にした甘いデザートワインの酔いも私の感覚を鈍らせてくれました。雲の上を歩くような気分で、私はいつの間にか帝国ホテルの一室に導かれていました。』
文春文庫「傾国子女」より
「文壇の貴公子」とも呼ばれる端正な顔立ちでスタイルも抜群のイケメン作家。多才な人で、小説、戯曲に加えて、オペラの台本も書けば演出もやり、作曲、歌手もやるといった具合で、俳優として映画にも出演している。
2013 年に発表した小説「傾国子女」は言うまでもなく「帰国子女」をもじったものだが、どうしようもなく男好きのする美貌に生まれてしまった絶世の美少女が、その運命を聖母の心境で受け容れ、集蛾灯のごとく次から次へと黙っていても寄ってくる男達と関わっていく物語。その男性たちの幅の広さがまたものすごく、少女偏愛者のロリコン小児科医から、暴力団組員、財界の黒幕、大物政治家(後に首相)を父に持つ遊び人の大学生、証券マンから政治家に転身した未来の首相候補、大学の哲学助教授、ホストクラブのホストなどだが、こうした一見するとかるーくさらりと描かれている登場人物の設定やキャラが、実は綿密な取材と知識に基づくもので、へたな経済学や政治学の教科書よりも世の中の仕組みがよくわかる。同じ年に発表されたホームレスになった元銀行マンのサバイバルライフを描いた「ニッチを探して」でも、銀行員の世界の暗い闇を軽いタッチで描いているが、これを松本清張あたりが書けば、おそらく暗いドロドロした粘着性のものになるのだろう。ユーモアをまぶした文体は口溶けがよく、サクサクと楽しく読ませるが、実は重いテーマが通底しているのも島田の作品の特徴だ。
言葉遊びやおちょくりは大の得意。おそらく照れ屋なのだろう。カタカナの「サヨク」や「ヒコクミン」を自称してみたり、瞠目反(アンチ)文学賞を主催したり、既存の価値感や体制に対して、少年が帽子をちょっとはすにかぶるような感じで、それってさ、ちょっと違うんだよね、と軽く頭をそらしてみせるのだが、普通は五十路を越えた中年オヤジがそういうことをやると意図むんむんでいやらしいも
のなのだが、島田の場合はスカッと軽やかに着地が決まる。
しまだ・まさひこ●1961年、東京生まれ。作家。東京で生まれたが、神奈川県川崎市育ち。東京外国語大学外国語学部ロシア語学科卒業。大学在学中、1983 年「優しいサヨクのための嬉遊曲」で作家デビューし芥川賞候補となる。1984 年「夢遊王国のための音楽」で野間文芸新人賞受賞。1992 年「彼岸先生」で泉鏡花文学賞を受賞。2006 年「退廃姉妹」で伊藤整文学賞を受賞。2003 年からは法政大学国際文化学部教授。2000 年〜2007 年まで三島由紀夫賞選考委員を務めた。芥川賞には6度候補になりすべて落選した記録を持つが、2010 年下半期より芥川賞選考委員をつとめている。
高村 薫
【月3万ポンドはたいても賄えない豪奢な四間続きの部屋】
『ハイドパークは雨の闇だった。シンクレアは、鍵の壊れた門から公園の散策路に入っていった。後方から追ってくるダーラム侯は、傘もささず、ジャケットもなく、カーディガン一枚の姿で裸足だった。(中略)シンクレアは、たった今、パークレーンに面した豪華なドーチェスター(ホテル)のスイートルームから飛び出してきたのだった。後ろから追ってくる男が別邸代わりに借り切っている四間続きの部屋だが(中略)ひどい散らかりようだった。』
「リヴィエラを撃て」新潮文庫より
ここしばらくは「晴子情歌」をはじめ「新リア王」など日本社会における政財界の深い闇の歴史を描くことが多い高村だが、かつては外国人を主人公にした作品もいくつかあり、舞台もイギリスやアイルランドが中心のサスペンス小説「リヴィエラを撃て」や、主人公と交わるスケールがけた違いの中国人青年が異彩を放つ「李謳」のような作品も書いていたことがあった。
「リヴィエラを撃て」は、日本、中国、イギリス、アイルランドを舞台に、二重スパイ、三重スパイが跳梁跋扈するサスペンス小説。ロンドンで近ごろ起きているロシア人の元二重スパイが毒殺されたり、されかかったりといった事件を地で行くようなストーリーだ。日本人に加えて、アメリカ人、英国人、アイルランド人、中国人の登場人物が複雑に絡み合いながら、国際諜報戦の闇が暴かれていく。読みふけっていると、これが日本人作家が書いたものだということをときどき忘れてしまうほど、アイルランドの市井の人々の日常生活シーンや、英国貴族たちのライフスタイル、英国人と中国人との隠微で微妙な関係性など、それぞれその世界に生まれ育った人でなければ知らないような屈折、憂い、かもしだす匂いや肌の触感までディテイルを描き出している。たとえば、飲み物ひとつとっても「僕は濃いアールグレイに、熱いミルクを半分」と言う男はどんなバックグラウンドの男なのか、はたまた「バカラのグラスでシャトー・マルゴーを飲み、ガラードの純銀のスプーンでフレッシュ・キャビアをすくう」食事をする女は…といった具合だ。
ホテルについても、所属するクラスやバックグラウンドによって使い分けており、飛び抜けて裕福な部類の英国貴族であるダーラム侯がロンドンの別邸がわりに使っているのは「ドーチェスター」だが、文中でT.S. と称されるある登場人物は、「彼の常宿は『ブラウンズ』だ」と描かれることにより、その人物像がわかる人には推量されるようになっている。
高村にはぜひまたこんな作品を書いて欲しいと切に思うのだが。
高村薫(1953 〜)
●作家。大阪府大阪市東住吉区生まれ。1975 年、国際基督教大学教養学部人文学科卒業(フランス文学専攻)。外資系商社に勤務の後、作家活動に入る。1990 年、「黄金を抱いて翔べ」で日本推理サスペンス大賞受賞。「マークスの山」で直木賞受賞。「レディ・ジョーカー」
で毎日出版文化賞受賞。「太陽を曳く馬」で読売文学賞受賞。主な作品に「レディ・ジョーカー」、「リヴィエラを撃て」、「わが手に拳銃を」を文庫化時に大幅に改稿しほとんど別作品と言われている「李歐」など。
橘 玲
【さすがに渋いホテルをお選びになるんですね。】
『榊原が指定したのは、日本大使館から近いオーチャードロードのフォーシーズンズだった。(中略)「大使館に来ていただくのは大仰かなと思って、ここにしてみたんです。昼食ならオーチャードホテルのホア・ティンかシャングリ・ラのなだ万がいいと思ったんですが、大通り沿いのホテルは観光客が騒がしくて、なかなかいいバーがないんですよ。ここはオーチャードロードから一本奥に入って落ち着いているので、ときどき使っているんです」
バーは木目調で統一された書斎のような雰囲気で、ビジネスマン風の客が何組かいるだけだ。』
「タックスヘイブン」幻冬舎文庫より
橘は「海外投資を楽しむ会」の創設メンバーのひとりでもあり、日本において海外投資を駆使した資産形成を提唱する金融コンサルタントの草分であることから、作家としてよりも、そっち方面でむしろ名前が知られているが、得意分野をベースにしたミステリータッチの小説も書いている。
「タックスヘイブン」は、シンガポールで最も成功したといわれる日本人ファンドマネージャーが、ホテルから墜落死する事件から物語は始まる。彼は有名政治家や闇世界のフィクサーたちのプライベートバンクの口座に十億円単位で穴を開けており、そこから生まれた1000 億円という大金をめぐり、生馬の目を抜く外資系プライベートバンカーや日本の大手銀行マン、闇世界の大物たちを相手に、法の網をかいくぐり、依頼者に渡そうという主人公の命をかけた真剣ゲームが展開する。その舞台として使われているのが世界各地のホテルなのだが、香港、シンガポールなどアジアの金融センターのホテル比較は、おそらく橘自身の経験を元にしているのだろう、実に的を得ている。主人公たる海外投資に詳しい金融コンサルタント・古波蔵がシンガポールの宿として選んだのは、「ザ・フラトン・ホテル・シンガポール」。1928 年に建てられたギリシャ神殿さながらのドーリア式円柱がある元中央郵便局だった建物をリモデリングしたホテルで、日本大使館員にわざわざ「ラッフルズかリッツだろうと思ったんですがお泊まりになっていなくて(中略)さすがに渋いホテルをお選びになるんですね」と言わせている。ここに泊まりながらマリーナベイサンズのクラブに遊びにでかける。
また、「マネーロンダリング」では香港が舞台になっているが、ここで橘が使うのは「グランドハイアット香港」。「温泉観光ホテルに成り果てたペニンシュラとはずいぶん雰囲気が違う」と書くなど、かなりのホテルジャンキーぶりを見せている。
橘 玲(1959 〜)
●作家。本名・写真は非公開。早稲田大学第一文学部卒業。宝島の編集者を経て、2002 年「マネーロンダリング」で作家デビュー。2006 年「永遠の旅行者」が第19 回山本周五郎賞候補となる。「海外投資を楽しむ会」の創設メンバーの一人で、2003 年には日経新聞で「日曜日の人生設計—もうひとつの幸福のルール」を連載し、海外投資に興味を持つ人々や相続に悩む資産家たちの間で話題になった。2014 年に出した「タックスヘイブン」がパナマ文書事件で再び浮上中。
谷崎潤一郎
【千九百十一年のブルガンディー酒がある】
『三井銀行の土屋君の紹介で、東洋第一、否世界中での有数な旅館と云はれる「マヂェスティツク・ホテル」と云ふのへ、話の種に二三日泊って見たが、宿泊料は一日最低が二十五弗、最高が七十五弗で、設備万端贅沢を極めてゐるに拘はらず、ボルド酒は千九百二十二年のシャトオ・ラフィツトが最上と云ふところ、長崎のジャパン・ホテルにだって千九百十一年のブルガンティー酒があるくらゐだのに、此れではちよっと貧弱である。料理も決して旨いとは云へない。』
「上海交遊記」みすず書房より
1926 年、当時、神戸に住んでいた谷崎は、上海へ行くため、一昼夜かけて寝台列車で長崎まで行き、当地で4、5日遊んだ後、日本郵船の上海便に乗船した。長崎で泊まったホテルが大浦町にあった当時、長崎ではトップクラスの「長崎ジャパンホテル」だった。このホテルについて谷崎が触れているのは、文藝春秋に書いた「上海見聞録」の中である。上海にて東洋一と言われる有名ホテル「マジェスティックホテル」に「話の種に二三日泊まって見たが」、料金が高く設備も贅沢を極めているにもかかわらず、ワインリストが貧弱で、料理もうまくないと文句を言っているのだが、そのワインの品揃えの比較に出されているのが「長崎ジャパンホテル」である。
谷崎が散々けなした「マジェスティックホテル」だが、1910 年に建てられた高級ホテルのひとつで谷崎が訪れた翌年の1927 年12 月に蒋介石と宋美齢がここで豪勢な結婚披露宴を行ない話題になった。谷崎はこのとき、上海ではもう一軒、別のホテルにも泊まっている。フランス租界や中心街の南京路に近い「一品香旅社」(一品香ホテル)で、ここに関してはホテルの評価についてはまったく触れず、上海在住の友人たちが「私の泊まってゐる一品香ホテルまで来て、紹興酒を飲みながら又暫らく談じ続け」「ホテル前の、競馬場に沿うた坦々たる西蔵路の大道を、車は二人を載せたまゝ北から南へ走つて行く。」とだけ記している。ちなみに、「細雪」のモデルにもなった三人目の妻・松子夫人と出会ったのはこの上海旅行から帰った翌年のことである。
谷崎は一流好みだと言われているが、旅先のホテルもその土地で一、二を争う有名ホテルを常に選んだようだ。また、神奈川県鵠沼海岸にかつてあり、庭の池ではボート遊びもできたという和風ビーチリゾートホテルのような「あづまや別館」にも長期滞在していたことがある。有馬温泉の「陶泉 御所坊」は定宿だった。
谷崎潤一郎(1886 〜1965)
●小説家。1886 年東京日本橋生まれ。府立第一中学校(現日比谷高等学校)在校時には学業優秀で神童と言われる。1908 年東京帝国大学国文科入学するが中退。「文章を書くことは余技であった」と後に述懐しているが、大学在学中に発表した小説「刺青」などの作品が永井荷風に激賞され、文壇デビュー。主な作品に「痴人の愛」「春琴抄」「細雪」「鍵」「瘋癲老人日記」のほか、「源氏物語」の現代語訳などがある。日本人では初の全米芸術院・米国文学芸術アカデミー名誉会員。
玉村豊男
【窓をあければ、パリの建物の屋根、煙突、屋根裏部屋の窓】
『パリでは、できることなら、アメリカ式ホテルやフランス式で大きな(高い)ホテルではなく、小さなやすいホテルに泊まりたい。カネがないからではなくて(実際にはそういう面の効用も実に大きいのだが)、そのほうがたとえ不便でもパリのムードが出るからだ。星のついてるホテルでもせいぜい一ツ星くらい。星がなくても夜道は暗くない。パリは光の都である。
<中略>
薄汚れているような感じはするがそれほど不潔ではなく、あやしげな感じがしないわけではないが決して危険ではない、そういうホテルがパリには多い。』
「パリ 旅の雑学ノート」新潮文庫より
玉村といえば、最近では、料理やワイナリー&レストランのオーナーとしての顔の方が知られているが、エッセイストとしてデビュー。1978 年刊のエッセイ集「パリ 旅の雑学ノート」が、本人いわく「非実用的なエッセイ」ブームの先駆けとなった。フランスのホテルのバスルームには必ずあるビデの使い方とか、フランス式風呂の入り方、日除け扉の閉め方など、旅行者が知っておくと役立つ実用っぽい情報も書かれているが、しばしば必要以上の詳しさや脱線した情報が盛りこまれており、これが実に楽しい。
ホテルの章では、「ホテルとバスルームの関係」を解きあかすなかで、ホテルの星の数がどのように決められているのかを詳細に解説。星の数はハードの設備によるものであって、サービスなどソフトはまったく関係ないことを初めて日本人に知らしめた。「極端なことをいえば、設備さえよければ、サービスは良くなくても、感じが悪くても、四ツ星の” 高級ホテル” になれる、というわけだ」と。
「フランス式ホテルのインテリア研究」では、アメリカ式とフランス式を比較した。ホテルの章の最初に出ている写真のホテルは『グランドテル タランヌ』(現 オテル・オ・マノワール・サンジェルマンデプレ)で、パリ左岸、サン= ジェルマン・デプレ大通りに面した小さなホテルである。いかにもパリのプチホテルといった風情のホテルで、隣が有名レストラン「ブラッスリー・リップ」であるため、リップの日除けのロゴをちらりと入れ、パリの街角シーンとして広告写真などによく使われている。二ツ星ホテルであるが、上で抜粋した玉村がパリで泊まりたい「小さなやすいホテル」とはおそらくこんなホテルなのではないだろうか?
玉村はそういうホテルの客層についてこう書いている。「客層はあまり経済的余裕のない外国人観光客、学生風の若者、田舎から出てきたディスカバー・パリのフランス人等々…。必ずしも人品卑しからず、危険人物はそういない」。実に的確な描写である。「私は宿に荷物を置くとすぐに街の匂いが嗅ぎたくなって外へ出る」という玉村は、高級ホテルよりも、街に溶けこんだ「小さなやすいホテル」を愛しているようだ。
玉村豊男(1945 〜)
● 1945 年東京生まれ。エッセイスト、画家。東京大学文学部仏文学科卒業、フランス留学を経てフランスや旅関係の執筆活動をはじめ、旅、料理、ワイン、田園生活をベースにしたライフスタイルに関する著作が多い。軽井沢に移住したことをきっかけに、ワイナリー、レストラン、ショップの経営を始め、株式会社ヴィラデストワイナリー会長。主な著書に「パリ旅の雑学ノート」「男と女のレストラン」「パリのカフェをつくった人々」など。
辻 邦生
【重々しい寝台や、ぎしぎし軋る衣裳箪笥】
『アレッツォで私が泊まったホテルは、有名なピエロ= デラ= フランチェスカの壁画のあるサン= フランチェスコ教会の並びで、古びた厚い壁や、時代ものの木彫のある重々しい寝台や、ぎしぎし軋る衣裳箪笥などが、いかにも歴史のなかに息づく古都の趣を感じさせた。教会の建物とホテルとが同じ一つの壁を共有して建てられているのも面白かった。町が丘の斜面にひろがっているため、どこに行くにも坂を登ったり、降りたりする。』
「地中海幻想の旅から」中公文庫より
フランス文学者で、パリが大好きで長く住んだ辻だが、イタリアについても強い憧憬を抱いていた。1990 年に刊行されたエッセイ集「地中海幻想の旅から」の冒頭で19 世紀イギリスの小説家ギッシングの言葉【イタリアのことを考えただけで私は切ない憧れに身を焦がれる思いであった】が引用されているが、これはそのまま辻の想いでもあったのだろう。【一度その魅力にひきこまれた人は、終生そこから逃れることはできない】とも書いている。上で引用したアレッツォのホテルの描写はイタリアのこうした古びたホテルに漂う空気、匂いを実に的確に伝えているが、これは同時に辻が愛した歴史と共に生きるイタリアでもあったのだろう。
北アフリカのコンスタンティーヌのホテルの描写では【ホテルの重苦しい飾りも、古めいた廊下も、植民地時代の栄華を偲ばせる】と記し、【ベル・エポック風の服装をしたフィッツジェラルドに、つい町角で行き交いそうになる気分を、この町は持っていた】と続け、ホテルを通して、そこにある時間を伝える。
辻はパリではホテル暮らしも長かった。1980 から没年の1999 年まで暮らしたパリ5 区デカルト通りあるアパルトマンを借りるまでは14 区のモンパルナス墓地に近い「オテル・エグロン」がパリでの定宿だった。「私の二都物語 東京・パリ」(1993 年、中央公論社刊)によると、【一年通して借りていても、2ヶ月のホテル代より 安い】と書いている。
辻の「愉しみ」をあらわす表現のひとつに【食後の上等なコニャックに似た味わい】というのがあるが、この本そのものが旅好きにとってはまさにそうだ。ニースでは【青い微笑するような地中海】を見て、ブリンディシから船でギリシャに行ったときは【地中海の青い、甘美な、和やかな波を、心ゆくまで味わった】、そして、辻が【この地中海の青さ— 夥しい青さとでも形容すべきこの色彩】を真に味わったのは南仏セートだったという。
辻はまたこうも書く。【この世の愉しみのなかで、私は旅する愉しみをその第一に数える】。生涯、旅に生きた作家である。
辻 邦生(1925 〜1999)
● 1925 年東京生まれ。小説家、フランス文学者。東京大学文学部仏蘭西文学科卒業後、大学院に進み1957 年から1961 年までパリに留学。1980〜1999 年までパリ5 区の住居で多くの時を過ごす。1963年、「廻廊にて」で近代文学賞、1973 年「背教者ユリアヌス」で毎日芸術賞、1995 年「西行花伝」で谷崎潤一郎賞受賞。「遥かなる旅への追想」「地中海幻想の旅から」「美しい夏の行方イタリア・シチリアの旅」など旅をテーマとした著作も多い。
辻 静雄
【目立たぬ行為に、ゆき届いた仕事をしているなあとホトホト感心させられる。】
『このホテルはラ・レゼルヴ・ドゥ・ボーリューといい、ニースからモンテ=カルロにむかって海岸沿いにしばらく走った所、ボーリュー=シュル=メールにある。部屋数五十ばかりの小さなホテルである。<中略>秋になると、いわゆる観光客は去り、コート・ダジュールは静かな物腰の人たちをチラホラみかけるくらいになる。そして、南仏だからもちろん明るく、各部屋が全部海に面していて、はなやいだ雰囲気をもっていることに変りはないのだが、小ちゃな入口、レセプション(フロント・デスク)、すぐ目と鼻の先にコンシエルジュ(番頭さん)がいるところ、なにもかもがささやかでしかも底光りするつくりなのである。<中略>
豪華なホテルに泊まり、これでもかというくらい上等な料理にアキアキした人たちが静かに食事をたのしみ、おいしいワインを飲み、物思いにふけり、昔話に花をさかせ、紺碧の空と海とを眺め、色とりどりの花に囲まれ……といった一夜をあかすのにはもってこいのホテルなのである。<中略>夜は、まばゆいばかりのシャンデリアの下、かすかに聴こえてくるピアノの調べにのって皆それぞれ思い思いにメニューから選ぶ。』
「ヨーロッパ一等旅行」新潮文庫より
辻静雄は、辻調グループの創設者であり、日本におけるフランス料理の伝道者、料理研究家などの肩書きで紹介されることが多い。しかし、彼の本領はなによりも物を書く人であったと思う。辻の書いたものを高く評価していたひとりに開高健がいるが、「パリの料亭」に寄せた「蛇の足」とタイトルをつけた解説文で、「豪奢は惜しまないけれど歌を歌としないという心得のある人物の書いたこういう紀行文は稀です」と評している。開高が見抜いていたのは、辻の背骨の髄にあった物書きの魂である。
労を惜しまない勉強家で、常に原典に当たり、二次資料だけでなく、必ず一次資料まで当たり、さらには現地に出かけて自分の眼と耳と舌で確かめた。へたな学者では太刀打ちできないほどの博識であると同時に、ホテルやレストランに行ったときに、そこのたたずまいから「本物さ」「一流」を構成しているものが何かを瞬時に見抜く力と感性、そしてそれを言葉で表現する力を持っていた人だった。
また、その店を評価する際、料理の良し悪しだけではなく、「その昔のギャルソンたちの立ち居振る舞いは、それ自体、芸術品だった」など、舞台の”主役”だけではなく、”脇役”たちにも目を向けた。辻の実家は本郷の和菓子屋なので、職人たちの世界を知識や言葉ではなく、体感として知っていたのだろう。
大阪読売新聞の社会部に3年在籍したが、記者1年目に仕事先で出会ったのが、割烹学校の経営者のお嬢さん、辻勝子(偶然に名字が同じ)だったのが、運命を変えた。
上で引用した文章は、「吉兆」のご主人、湯木貞一氏とその息子さんたちを連れてヨーロッパの一流ホテルに泊まり、一流レストランを食べ歩いた旅の記録である。ヨーロッパ各地に定宿を持ち、パリでは「ル・ブリストル」を好んだ。ドイツのバーデンバーデンに通うのは、「ここにはブレンナーズ・パーク・ホテルというのがあって、宿はこの一◯九号室でなければならないのだとは、こだわりすぎか」。
すべてにこだわりぬいた人生だった。
辻 静雄(1933〜1993)
●東京、文京区本郷生まれ。辻調グループの創設者、料理研究家。生家は和菓子店。早稲田大学文学部仏文学科卒業後、1957年、大阪読売新聞社入社。1960年、同社を退職して妻の実家を継ぎ、大阪・阿倍野に辻調理師学校を開校。1964年、初の著書「フランス料理 理論と実際」。TBS系列テレビ番組「料理天国」の番組監修を担当。料理の専門書に「フランス料理 理論と実際」、フランス料理の技術とサービスの両面の歴史をまとめた「フランス料理研究」など。一般向けの著書に「パリの居酒屋 びすとろ」「パリの料亭 れすとらん」「ワインの本」「ヨーロッパ一等旅行」「料理に『究極』なし」など。
東野圭吾
【髪を綺麗に刈ったホテルマンは丁寧な口調で】
『パークサイドホテルの歩行者用入り口は道路沿いにあったが、正面玄関に行くには、そこから敷地内の庭園を歩かねばならなかった。千都留は重い荷物を手に、曲がりくねった細い歩道を進んだ。(中略)
ようやく正面玄関に近づいてきた。タクシーが次々と入ってきては、その前で客を降ろしている。やはりこういうホテルに来る時には、車でないと格好がつかないなと千都留は思った。ホテルのボーイたちも、徒歩でやってくる客には関心がなさそうだ。』
「白夜行」集英社文庫より
東野圭吾とホテル、といえば「マスカレード・ホテル」シリーズが有名だが、この作品の舞台のモデルになっているのは、東京・水天宮の「ロイヤルパークホテル」。かつて近くの清洲橋に住んでいた東野は編集者との打ち合わせにロビーラウンジをよく使っていたそうだ。そのせいか他の作品でもホテルのラウンジのシーンが登場することが多い。「幻夜」では刑事が「コーヒー一杯で千円もするぜ」と値段の高さに驚き、相棒が「おかわりは自由のはず」と返すシーンがある。
「マスカレード・ホテル」はストレートなホテルものだが、東野は他の作品でもしばしばホテルを舞台に使っている。
1999 年に出版された「白夜行」はホテルシーンが多い小説のひとつだ。大手製薬メーカーの創業者一族の御曹司が大学在学中、恋人の女子大生と泊まるのは「大阪のシティホテル」とだけ書かれている。ホテル名はつけず、さらりと。御曹司のホテルの使い慣れを示すシーンだ。
一方、ヤクザの女と火遊びする素人の青年が逢引に使うのは「心斎橋にある新日空ホテルの喫茶ラウンジ」。「ホテル日航大阪」であることがみえみえだ。
東京・成城の代々の大地主の息子と主人公の女性が結婚式を挙げた「ここのフレンチおいしいのよ」という「赤坂のホテル」とは、「ニューオータニ東京」と赤プリのどちらだろうか?
東京で働いていた派遣社員の女性が地方の実家に戻る前、最後の贅沢にと品川駅前のシティホテルにひとり泊まりするのが上記に抜粋したシーンだが、1999 年当時「一泊1万2千円から」というホテルは、おそらく旧「ホテルパシフィック東京」だろう。それより「はるかに格上」な「品川の奥にあるホテル」とは。旧「高輪プリンス」、それとも旧「都ホテル東京」だろうか。そこの「四万円の部屋」を用意するから予約を譲ってくれないかと頼まれた女性は「自腹では絶対に泊まることのない部屋だ」と快諾する。
東野圭吾(1958 〜)
●小説家。大阪市生野区生まれ。大阪府立大学工学部電気工学科を卒業後、エンジニアとして日本電装株式会社(現デンソー)入社。高校在学中より小説を書き始め、1985 年に「放課後」で江戸川乱歩賞を受賞し専業作家になる。2006 年、「容疑者Xの献身」で直木賞受賞。同書はアメリカ図書館協会最高推薦図書(ミステリー部門)にも選ばれた。2014 年「祈りの幕が下りる時」で吉川英治文学賞受賞。主な作品に、「秘密」「手紙」「白夜行」「幻夜」「マスカレード・ホテル」、ガリレオシリーズの「真夏の方程式」など。
常盤新平
【いつもひっそりとして、ボーイが親切で。】
『彼女は礼儀正しいボーイに注文を言った。
「トマトジュースに、このパセリ入りのオムレツ(とメニューをさす人差指はほっそりとして白い)とシナモン・トースト、それにコーヒー」
よく澄んだ声。アルトよりちょっと高い感じ、頭をあげてボーイを見る眼が、少女のように大きい。(中略)
ボーイが去ると、二つに折ったうすい雑誌を白いリネンのテーブルクロスにひろげた。「ニューズウィーク」です。』
大和文庫「ニューヨークの女たち」より
常盤は、エッセイ集「ニューヨークの女たち」で「プラザホテルの前のピューリッツァーの泉で遊び、五番街を猛烈なスピードで車を飛ばした。」とスコット・フィッツジェラルドとその妻ゼルダ夫人について描くことで、1920 年代のニューヨークに満ちていたジャズエイジの気分を短いワンセンテンスで描ききった。
常盤の代表作といえば、アーウィン・ショーの「夏服を着た女たち」の翻訳だろう。そこでショーが主人公に「僕はオフィスで働く女が好きだ。小ざっぱりしてて、眼鏡をかけて、スマートで、朗らかで、なんでも知ってて、自分のことは自分で始末する」と語らせるシーンがあるが、「ニューヨークの女たち」を読むと、常盤の好きな女のタイプ” ミス・ニューヨーカー” はショーとよく似ているようだ。実際、常盤は同書でこう書いている。「アーウィン・ショーの短編に登場する女たちが素晴らしい。知的で都会的な美女たち。私が名づけたミス・ニューヨーカーである。ニューヨークの五番街の、なんともいえないソフィスティケーテッドな雰囲気を伝えてくれる。」。
上の引用文は同書の「ようこそ、ミス・ニューヨーカー」という項からの抜粋だが、ここでどんなタイプの女性が常盤のいうところの” ミス・ニューヨーカー” なのかを説明するために、『山の上ホテル』のダイニング・ルームでひとり朝食をとる女性のシーンを書いている。ファッションも「一見、平凡である。流行におくれてはいないが、流行にさきがけてはいないし、流行にのってもいない」そうで、「ミス・ニューヨーカーに会うとしたら、どこがいいか」という自問に対してあげている場所は、「彼女がパセリ入りのオムレツをたのんだ山ノ上ホテル、本館のダイニング・ルームがいいと思う」とホテルのみならず館内のレストランの指定付きで、その理由は「いつもひっそりとして、ボーイが親切」だから。ほかに挙げられている場所は、「高輪プリンスのティー・ラウンジ」「ホテル・オークラのエレベーターのなか」などホテルが多い。そんなふうに、常盤はホテルというものをさまざまなシーンの舞台として見ていたようだ。
常盤新平(1931 〜2013)
●作家、翻訳家、アメリカ文化研究者。岩手県生まれ。早稲田大学文学部英文科卒。同大学院修了後、早川書房に入社。ミステリー小説誌「 エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン」(日本版)の編集長を1963 年から6 年間務め、「ハカヤワ・ノヴェルズ」を創刊。1969 年早川書房を退社してフリーに。1986 年、自伝的小説「遠いアメリカ」で直木賞受賞。主な翻訳作品に、アーウィン・ショーの「夏服を着た女たち」、ゲイ・タリーズの「汝の父を敬え」など。ノンフィクションに「山の上ホテル物語 」など。「マフィアの噺」「マフィア経由アメリカ行」などマフィアについての著作も多く、マフィア研究家としても知られている。
夏目漱石
【此処へ来て一夏気楽に暮らしたい】
『室の中に這入ると、寝床には雪の様な敷布が掛っている。床には柔らかい絨毯が敷いてある。豊かな安楽椅子が据えてある。器物は悉く新式である。一切が整っている。外と内とは全く反対である。満鉄の経営にかかるこのホテルは、固より算盤を取っての儲け仕事でないと云う事を思い出す迄は、どうしても矛盾の念が頭を離れなかった。
食堂に下りて、窓の外に簇がる草花の香を嗅ぎながら、橋本と二人静かに午餐の卓に着いたときは、機会があったら、此処へ来て一夏気楽に暮らしたいと思った。』
「漱石紀行文集」岩波文庫より
どこに行っても、何をやっても、どうにもピタッとこない違和感を感じ続けた生涯だったようだ。裕福な名主の家に生まれるも生後すぐに養子に出され、養子先では養父母が離婚、7才で生家に戻り祖父母と思っていた人が実の親であることを知ったりと、生い立ちは複雑。病弱で肺結核、胃潰瘍、糖尿病にリウマチを患い、痔にも悩まされる。精神的にも神経衰弱、強迫観念に苛まれ、妻もノイローゼ気味で自殺未遂事件を起こすなど家庭も落ち着かない。そんな暗さの要素オンパレードな人生のなかで書かれたのがユーモアあふれる「我輩は猫である」や「坊ちゃん」だったりする。
1909 年、大学予備門時代の下宿仲間のひとりで満鉄総裁となった中村是公に招かれ、満州と朝鮮を旅した。是公は夏目の親友としても知られた人物だ。当時、夏目は朝日新聞の社員となっており、この旅の旅行記は「満韓ところどころ」(「漱石紀行文集」に収録)として朝日新聞に連載された。
夏目は「おい、ぜこう(是公の愛称)」と呼びすてにするが、現地では泣く子も黙る満鉄総裁。宿泊先は満鉄直営のヤマトホテルグループのホテルである。夏目の訪満当時は大連、旅順、長春にあった。「大連ヤマトホテル」はロシア時代のダルニーホテルを改修したもので、夏目が滞在した頃は47 室(後に新館に移転して100 室に拡張)。経営は赤字続きだったらしく、「四辺が森閑としている。ホテルの中には一人も客がいない様に見える」と夏目が記している。
旅順では「おい旅順に着いたら久し振りに日本流の宿屋に泊まろうか」と同行者に言うが、相談した現地の人からは「矢っ張り大和ホテルに為さった方が好いでしょう」と言われる。
夏目が胃潰瘍の転地療養のため滞在し大量吐血して危篤状態になったのは伊豆修善寺の「菊屋旅館」。正岡子規と共に初めて訪れた京都で泊まったのは「柊屋」。
夏目漱石(1867 〜1916)
●小説家、評論家、英文学者。1867 年、江戸の牛込馬場下横町生まれ。東京帝国大学英文科卒業後、高等師範学校等の英語教師を務め、文部省に派遣され英語教育法研究のために1900 〜1902 年、イギリスのロンドンに留学。帰国後、東京大学で英文学を教えるかたわら、高浜虚子の勧めで「ホトトギス」に書いた小説「我輩は猫である」で1904 年作家デビュー。続いて書いた「坊ちゃん」「倫敦塔」も好評で、朝日新聞社に籍を置きながら執筆を行う。主な作品に「草枕」「三四郎」「それから」「門」「行人」「こころ」など。
林 真理子
【そうね。それがこのホテルでのいちばん正しい過ごし方よ。】
『「バンコクで泊まるなら、絶対にマンダリン オリエンタルよ。他にも新しいところがいろいろ出来たけれど、あそこほどバンコクにいる時間を楽しませてくれるところはないのだから」
志帆子はそうメールに書いてきた。(中略)
「私はいつも旧館のオーサーズ・スイートに泊まることに決めてるの」(中略)
広いロビーをつっきり、アーケード・ショップの中を通って、旧館のロビーに出た。コロニアル風の白い螺旋階段で、母のいる二階へと向かった。この旧館は創業当時のものらしい。「ジェイムズ・A・ミッチェナー」と記されたドアをノックする。中からドアが開き、白いTシャツにカーゴパンツといういでたちの志帆子が立っていた。(中略)
「ママ、どうしたの、すごくきついにおいだわ」「これはエルメスのジャルダン アプレ ラ ムッソンよ。日本語でモンスーンの庭っていうの。私はこのホテルに泊まる時は、いつもこれをふりまくのよ。ベッドにもバスルームにもね」
東京で会う時の母と、まるで違っていることにれおなは気づく。(中略)
こうしてくつろいだ格好をして、強い野性的な香水のにおいをさせる母は別人のように見えた。』
「アスクレピオスの愛人」新潮文庫より
1980年代のはじめ、時代がバブルに向かってまっしぐらに進んでいた頃、気鋭のコピーライターとして時代の先端を疾走する “業界人”たちのひとりだった。西友ストアの広告コピー「つくりながら、つくろいながら、くつろいでいる。」でTCC(東京コピーライターズクラブ)新人賞を受賞し、フジテレビのキャンペンガールにも抜擢されたりしたが、早々に広告業界には見切りをつけ、エッセイスト、小説家へ転進した。
1983年刊行の第2作目のエッセイ「夢見るころを過ぎても」(主婦の友社)では、大学卒業後も就職できずに一間のアパートで貧乏暮らしをしていた頃、同じアパートに住む同じような懐具合の友人がシティホテルに泊まってきた話を、「少なくとも彼女はホテルの朝食のグレープフルーツジュースの味を知っている」と書き、このワンフレーズでその女性の生き方を表現した。
その後、売れっ子女性作家となり、海外旅行にもひんぱんに出かけ、世界各地の高級ホテルの滞在経験を雑誌のエッセイなどにもよく書いている。1990年には36歳でサラリーマン男性と見合い結婚。披露宴は「ホテルニューオータニ東京」のフレンチレストラン「トゥール・ダルジャン」で当時はまだ珍しかったレストランウェディングを行い、披露パーティーは旧赤坂プリンス旧館で行った。
上記で抜粋した「アスクレピオスの愛人」はジュネーヴに住むWHOのメディカル・オフィサーの女性を主人公に、彼女を巡るさまざまな境遇の医師たち、医療に関わる人々の世界を描いたものだが、ホテルがいくつか登場する。富裕層むけの高級クリニックから総合病院、私立医大など医療ビジネスのやり手の恋人との逢瀬のためパリで落ち合う際は「フォーシーズンズホテルのスイート」。「フォーシーズンズ・ホテル・ジョルジュサンク」のことだ。WHOの出張で東京に滞在する際には、「新宿にある外資系ホテル」…これはおそらく「ヒルトン東京」だろう。主人公が娘とバンコクで落ち合うホテルとして「マンダリンオリエンタル」を舞台に選んでいるが、ここの描写は詳細だ。
林 真理子(1954〜)
● 作家、エッセイスト。山梨県山梨市生まれ。日本大学藝術学部文芸学科卒業。就職活動に敗れて、コピーライター養成講座に通学中、糸井重里氏の目にとまりコピーライターに。フジテレビのキャンペンガールになるなど幅広く活躍中の1982年、エッセイ「ルンルンを買っておうちに帰ろう」がベストセラーになる。1985年「最終便に間に合えば」で直木賞、1995年「白蓮れんれん」で柴田錬三郎賞、1998年「みんなの秘密」で吉川英治文学賞を受賞。NHK大河ドラマになった「西郷どん」のほか、「不機嫌な果実」「下流の宴」などテレビ化された作品も多い。日本文藝家協会 理事長。
平岩弓枝
【ホテルは、プラザ・アテネである。】
『「六月のパリのことですが、坪井先生の常宿は、どちらですか?」(中略)
坪井東作はプラザ・アテネへよく泊まった。
パリでは老舗である。
シャンゼリゼを凱旋門へむかって、アベニュー・モンテーニュを左折したあたりにあって、ナポレオン三世時代に開業したホテルである。
交通の便も悪くないので、明子も、佐伯信吉とパリへ行った最初は、叔父の紹介で、このホテルに滞在していた。
「もっとも、叔父は、セーヌ河に近くて、とても小さなホテルなんですけれど、四つ星で感じのいい宿も知って居りますの」』
「午後の恋人」集英社文庫より
平岩の小説に登場する主人公の女性は、センスがよく、料理上手。特に料理は、手元にあるもので手際よくササッと洒落た献立を仕上げる。またコーヒーや紅茶、ケーキ(特にパイのこだわりがすごい)、そして朝食のパンやジャムにもこだわっている。こういう人はたいていホテル好きであるが、ホテルを舞台にした作品が多い。
「午後の恋人」は、1974年に発表された作品だが、海外へ渡航する日本人の数は今の五分の一くらしかいなかった当時、パリのプラザアテネだの、マドリッドのリッツだの、スペインのパラドール(元城とか、貴族や領主の館、修道院などの歴史的建物を宿泊施設にスペインの国営ホテル)だの言ってもわかる人は非常に限られていた時代に、それぞれの街で目的に合わせ、こだわりがあるホテルを選んでいる。
特に主人公・明子の叔父として登場する、日本よりもむしろ海外で有名だという田園調布に住む画家の坪井東作は、非常に裕福であり、違いと贅沢をよく知る男として描かれているが、彼のパリの常宿はプラザ・アテネだが、「セーヌ河に近くて、とても小さなホテルなんですけれど、四つ星で感じのいい宿も知って居りますの」といった具合だ。また、プラザアテネの部屋の選び方もいかにもホテル慣れしており、叔父と姪の二人で2ベッドルームスイートを予約し、同行の画商と三人で夕食後、ナイトキャップをリビングルームで楽しんだりする。
「京都の蹴上にあるホテル」と書かれているホテルは、有名画家の常宿でもあり、おそらく都ホテル(現「ウェスティン都ホテル京都」)であろうと思われるが、離婚して独り身になった明子は、大晦日の夜をここでひとり泊まりして過ごすのだが、外で食事をして帰ってきたあと、ちょっと飲み足りないと思った明子に、平岩は「このホテルのバアはバーテンだけで、女一人で入っても、居心地は悪くない。以前、(中略)飲みに行った時も、外人の女性旅行客らしいのが、一人でブランディを飲んでいて、それが、なかなか悪くなかったのを、明子はおぼえていた。」こう語らせ、女ひとり泊まりのホテルの楽しみ方まで指南している。なかなかのホテルジャンキーと思われる。
平岩弓枝(1932〜)
●作家、脚本家。東京の代々木で鎌倉時代から続く神社、代々木八幡宮のひとり娘として生まれ育つ。先祖代々受け継いできた神職は同じく作家を目指していた夫が婿養子となって継いだ。日本女子大学国文科卒業。1959年、「鏨師」で直木賞受賞。「花影の花」で吉川英治文学賞。2010年、菊池寛賞受賞。1974年に書き始めた「御宿かわせみ」シリーズは約40年続いているロングセラー。脚本家としても知られ、テレビドラマの「ありがとう」、「肝っ玉かあさん」シリーズ、NHK大河ドラマ「新・平家物語」などヒット作が多い。非常に多作で、小説はテレビドラマ化されることも多かった。
三島由紀夫
【部屋は二人の閉じこめられた牢になった】
季節外れの閑散なホテルの一室で、かれらは最初の一夜をすごした。
(中略)
電話で注文した朝食が、朝日にまばゆい窓辺にはこばれるのを、仮りにガウンをまとっ
た土屋が迎えて、伝票に署名すればよかった。—— 朝日は寝台の裾のほうを犯している。窓
ぎわの卓の白い卓布の上には、今しがた用意された朝食の、銀の珈琲ポットが輝いている。
ナプキンに包まれたトーストの香りがしている。
(中略)
ではお給仕をいたしましょう、と窓ぎわに立っていた土屋が言って忽ちガウンを脱ぎ捨てた。
「美徳のよろめき」新潮文庫より
三島といえばまず思い浮かぶのは、日本ばなれした白亜の洋館の邸宅である。結婚の翌年に建てたそうだが、ヨーロッパ風の庭には大理石のアポロ像があり、吹き抜けの暖炉がある応接間など、三島
いわく「スペイン植民地風の家」である。そんな感性をもった男が好んだホテルとは、どんなホテルなのだろうか。
昭和30 年代の” よろめきブーム” のきっかけになった小説「美徳のよろめき」で、良家夫人である優雅なヒロインの” 姦通”の舞台となったホテルが軽井沢の『万平ホテル』。ルームサービスの朝食時の「真裸の朝食」シーン(上記抜粋)が有名だが、「銀の珈琲ポット」、「ナプキンに包まれたトーストの香り」などが、この老舗ホテルに漂う空気感を端的に語っている。宿帳には三島のサインが残っているが、職業欄には自ら” 文士” と書いた。123号室がいつもの部屋で、レストランでは虹鱒のムニエルをよく注文したという。
「バンコクは雨季だった。」という出だしで始まる遺作「豊饒の海」第三巻の「暁の寺」は、バンコクのチャオプラヤ河越しにのぞむワット・アルン寺院をモチーフに書かれた小説だが、舞台となってい
るのは、『アルン・レジデンス』付属のレストラン「ザ・デッキ」。三島が取材のためバンコクを訪れたのは1967 年のことだが、宿泊先は同じくチャオプラヤ河沿いに建ち、当時はバンコクきっての名門
ホテル「ジ・オリエンタル」(現『マンダリンオリエンタル・バンコク』)である。
こうした仕事で泊まったホテルとは別に、三島が毎年夏になるとプライベートで家族と訪れたのが、伊豆下田の『下田東急ホテル』である。1964 年から1970年の自裁の年まで7年間、家族とともに約1ヵ月間滞在し、地元の人々との交流も楽しんだという。「月澹荘綺譚」が書かれたのもここで、三島が好んで散歩していた遊歩道も作中に登場する。最後の夏に訪れた際、「もう来年は来られません」と地元の親しい知人に語っていたという。
三島由紀夫(1925 〜1970)
●小説家、劇作家。東京都新宿区生まれ。小学校より学習院で学び、13 才で小説を書きはじめ、16 才
の時、同人誌に「花ざかりの森」をペンネーム・三島由紀夫の名で発表。東京帝国大学法学法律学科在学中より川端康成に師事する。卒業後、高等文官試験に合格し大蔵省入省。執筆も併行して執筆も続けるが、1948 年作家活動に専念すべく退職。主な小説の作品に「仮面の告白」「潮騒」「金閣寺」「美
徳のよろめき」「午後の曳航」「豊饒の海」など。民兵組織「楯の会」を主宰し、1970 年、自衛隊市ヶ谷駐屯地で演説の後、割腹自殺。
村上 龍
【外国の古いホテルみたいね、目を輝かせて耳元で囁いた】
『ホテル・オーシャンパークスは断崖の上に建っている。屋根瓦がオレンジ、壁は白で地中海風の造りである。玄関に乗りつけると金モールの制服を着た送迎係が駆け寄ってきた。お泊まりでございますか? 助手席の扉を開けて目礼する。吉野愛子は緊張ぎみにスカートの裾を何度も直しながら車から降りた。車が450SLC で良かったなあ、胸の動悸を抑えながらテニスボーイは思った。サニーのライトバンなんかで来たら、あのボーイの奴らバカにするだろうなあ。』
集英社「テニスボーイの憂鬱」より
上で抜粋文を紹介した「テニスボーイの憂鬱」は、「限りなく透明に近いブルー」でデビューしてから9年目、5作目の作品で、1985 年に発表されたものだが、幻冬舎社長の見城徹氏によると、当時、角川書店の編集者だった見城氏と二人で角川の経費で「川奈ホテル」の一番高いスイートに年の四分の一くらい泊まり、「美食の限りを尽くして遊び」毎日テニスばかりしていた2年間のホテル体験を題材にして書いたそうだ。「ホテル・オーシャンパーク」として描かれているが、設定は「川奈ホテル」ほぼそのままで、ロビーでは「外国人の男女がベルボーイを侍らせてお茶を飲んでいた」り、「エルメスの揃いのスーツケースを十数個並べて」絵葉書を書いていたりと、プリンスホテルの傘下に入る前の「川奈ホテル」の古き良き時代が描かれている。ガールフレンドと同じ部屋に泊まる主人公がフロントで「一部屋でいいんだ」と「少し震え声」で言ったり、「連れてきた女がモデルでよかったなあ」とほっとしたり、名門ホテルにビビりながら泊まる若者の心情が初々しい。
村上にはホテルを舞台にした作品は多い。特に1989年に発表されてベストセラーになり、映画化もされた「ラッフルズホテル」はシンガポールのクラシックホテル、ラッフルズを舞台にしたもので、主人公の女性もこのホテルにつとめるホテルウーマン。このホテルを知っている人にとっては、「ああ、これって、あそこね」と思い浮かぶホテルシーンが数多く登場し、ホテルジャンキーにとっては楽しい作品である。
一方、あまり楽しくない設定でホテルが舞台に使われているのは、2005年に発表された「半島を出よ」。北朝鮮の特殊部隊が九州に上陸し、あっという間に福岡ドーム(現Yahoo ドーム)、シーホーク・ホテル(現「ヒルトン福岡シーホーク」)などホークスタウン一帯が占拠されるという、現実にあってもおかしくないようなストーリーで、北朝鮮の進駐軍が接収したホテルに占領のヘッドクオーターを置くのだが、ホテルの建築・つくりやさまざまな機能もストーリー展開に使われていておもしろい。
村上は、美術教師の父、数学教師の母のもと佐世保で生まれ育ち、幼少の頃から文才を発揮していたそうだ。ロックと学生運動に明け暮れエネルギーを持て余していた少年は、上京して米軍基地の近い福生に住む。通称 ”ムサビ” 、武蔵野美術大学に進み、在学中に書いた小説「限りなく透明に近いブルー」で芥川賞をとる。時は1976 年、本格的なバブル景気まではまだ10 年ほどの間はあったものの、「なんとなくクリスタル」(1980 年文藝賞受賞)の作者・田中康夫も ”ムサビ”のすぐ近くの一橋大学に在学中で、世の中の空気はすでに変わり始めていた。
「テニスボーイの憂鬱」がマガジンハウスの雑誌「BRUTUS」で連載されていたのは、まさにそんなバブル前夜の1982 年~ 1984 年だった。世田谷の土地成金のドラ息子で齢30 才・妻子あり、という小説の主人公のような男が東京にはゴロゴロいた頃で、彼らが若い女の子と待ち合わせる場所は、1980 年にオープンしたばかりの新宿副都心の高層シティホテル「センチュリーハイアット」(現 ハイアットリージェンシー東京)のラウンジ・バー、なんていう時代だった。当時の「センチュリーハイアット」の客層が詳細に描かれているが、【金もないくせにホテルで会い食事し最上階のバーで飲んで何とかものにしようという安サラリーマン風の男とヤボったいファッションの女だ。そんなカップルは見ていて悲しくなる。そんなカップルは必ず男の方がほとんど無意味な自慢話をしている。】など、村上の眼は厳しいが、上京してから東京出身のシティボーイたちのナチュラルな軽さやものなれた遊びっぷりに圧倒されたであろう地方出身者の自虐にもみえる。
そして、後の作品でもそうだが、バブルが崩壊した後がどうなるのか、時代の先を予想しているような世界を描いている。
村上は海外の高級ホテル体験も豊富で、「料理小説集」ではコートダジュールの「ル・キャップ・エステル」をはじめ世界各地のホテルシーンを描いている。ホテルは彼の小説にとって重要な “道具” のひとつのようだ。
芥川賞の選考の際、吉行淳之介が「因果なことに才能がある」と評したその才能は、吉行の予想どおり、文学の世界だけでは収まらなかった。
村上 龍(1952年〜)
●作家、映画監督。長崎県佐世保市出身。武蔵野美術大学造形学部基礎デザイン科在学中の1976年「限りなく透明に近いブルー」で群像新人文学賞と芥川賞を受賞。主な作品に「コインロッカー・ベイビーズ」「愛と幻想のファシズム」「五分後の世界」「希望の国のエクソダス」など。シンガポールのラッフルズホテルを舞台に描いた小説「ラッフルズホテル」映画化の際には、監督もつとめた。1999 年より、日本の金融・政治経済関連の問題を考えるメールマガジン「JMM」を主宰。
百田尚樹
【山王ホテルは帝国ホテル、第一ホテルと並ぶ東京を代表する近代ホテルである】
「そんなある日、東京支社にいた鐡造は満州国国務院の星野直樹総務長官から、秘書を通して「会いたい」という連絡を受けた。満州国の国務院の総務長官と言えば、日本の総理大臣に相当する。そんな男が山王ホテルにて極秘裏に会談したいと言ってきたのだ。赤坂にある山王ホテルは帝国ホテル、第一ホテルと並ぶ東京を代表する近代ホテルである。
山王ホテルに行くと、星野が豪華な部屋に暗い顔で座っていた。」
講談社「海賊とよばれた男」より
書きたいテーマがあれば小説家として小説も書くけれど、同時に構成作家としてテレビのバラエティ番組の構成も手がければ、政治問題など言いたいことがあれば、テレビ、雑誌などのメディアで発言、SNS で自ら発信もする。百田の活動は多岐にわたり、アクティブである。何かとお騒がせ発言も多く、メディアに登場する機会も多い。作家としてのデビュー作「永遠の0」が映画化もされ、300万部という大ベストセラーになったがゆえ、逆に作家としてはきわもの的扱いも受けてきた。
「海賊と呼ばれた男」も400万部を超える人気作品だが、出光興産の創業者・出光佐三氏をモデルとした小説である。明治時代に生まれたひとりの男が、既存のエスタブリッシュメント、権力に対して真っ向から闘いを挑み、道なきところに道をつくっていく物語だが、さまざまなシーンにホテルが舞台として登場する。
戦前の満州においては、満鉄がその街を代表する格式ある高級ホテルとしてつくった各地のヤマトホテルが、商談の場や出張先の宿泊先としてしばしば登場する。ヤマトホテルとは満鉄ホテルチェーンの高級ホテルブランド名だが、「長春(のちに新京に名称変更)ヤマトホテル」は1909 年、帝政ロシアや清国の高官との交渉の場にも使われた。客室数25 室で、アール・ヌーヴォー様式の高級ホテルとして知られていた。
また、1950 年代のイランの避暑地シミランの「観光用の一流ホテル」であった「ダルバンド・ホテル」は、出光興産が「海賊」呼ばわりされることになる命運がかかった交渉のための出張で泊まるホテルとして登場するが、「石造りの立派な建物だったが、外装もインテリアもメンテナンスが行き届いていない印象だった」と書かれている。
日本国内で、日本の高官との面談シーンでしばしば登場するのは「帝国ホテル」だが、上の引用文のように、「帝国ホテルと並ぶ東京を代表する近代ホテルだった」今はなき「山王ホテル」なども出てくる。海運会社との密談シーンでは、これも今はなき「日活ホテル」の最上階の食堂の「窓際の離れた席」が使われるなど、当時の東京のホテル事情がうかがえておもしろい。
百田尚樹(1956 〜)
●テレビ構成作家、小説家。大阪府大阪市出身。同志社大学法学部中退。在学中より放送作家としてテレビのバラエティー番組の構成を手がける。2006年、第二次世界大戦時のある特攻隊員の生き方を描いた小説「永遠の0」で作家デビュー。同書は300万部を超えるヒットとなり、映画化もされた。2013年、「海賊とよばれた男」で全国の書店の店員が売りたい本として投票する本屋大賞を受賞。ほかの作品に「夢を売る男」「フォルトゥナの瞳」「カエルの楽園」など。
森村誠一
【ホテル商品たる客室は一夜毎に腐る。】
『内外からの様々の客、明るく朗らかな客、むっつりとおし黙った客、尊大な客、おどおどしている客、饒舌な客、疲れている客、未知の邦への期待に燃えている客、旅馴れた客、観光客、商用客、休養客、そして情事や犯罪の匂いのする客、外国元首、大臣、役人、学者、医者、判検事、弁護士、サラリーマン、教員、神官、僧侶、学生、老若男女、白黒黄褐色、大中小、太いのと細いのと、個人(バラ)と団体(グループ)と……そこにはありとあらゆる種類の人間と人生があった。
ホテルでは人間の “万博” が毎日毎夜開かれているのである。』
「銀の虚城」廣済堂文庫より
森村誠一といえば、テレビCM でも繰り返し流された「ママぁ〜 ドゥーユー・リメンバー?」の主題歌と共に思い出される映画「人間の証明」の麦わら帽子を投げるシーンを思い浮かべる人も多いと思うが、その原作の舞台になったのが東京・赤坂の「ホテルニューオータニ東京」である。
ホテルマン出身の作家として知られる森村であるが、そもそもはホテルマンを志望していたわけではなく、卒業時が就職難時代でもあり志望していたマスコミの入社試験にことごとく落ちたため、大阪の新大阪ホテル(現「リーガロイヤルホテル」)の重役の姪だった妻のコネで同ホテルに入社した。数年後、系列の東京にある「都市センターホテル」に移り、東京オリンピックに向けて開業間もないホテルニューオータニに転職。こうして約10 年間のホテルマン生活を送った。
森村自身、「あの十年弱のホテルマン生活がなかったなら、私は作家になれなかったかもしれない。なったとしても別のジャンルの作家になったであろう」と「作家の礎石」(「森村誠一読本」)で語っている。
都市センターホテル勤務時代、ホテルの斜め向かいに文藝春秋新社屋ができ、同ホテルには笹沢左保、阿川弘之、黒岩重吾、五味康祐などの作家たちがしばしば滞在し、彼らと交流を持ったことも作家をめざすきっかけになったそうだ。ここを常宿にしていた、当時新進の人気流行作家、梶山秀之からは出版社に渡すよう頼まれ原稿をよく預かり、編集者に渡す前に読んで刺激を受けたという。
ホテルを辞め作家に専従するまでの2年間は東京スクール・オブ・ビジネスで講師もつとめた。こうして業界に知悉しているせいか「銀の虚城」など初期のホテルを舞台にした作品では、ホテルマンの視点から見た世の中、ホテルマンたちの社会、ホテル界について言いたいこと書きたいことがありすぎてもどかしい感じが読み手にも伝わってくるほどだ。
森村誠一(1933 〜)
●小説家。埼玉県熊谷市生まれ。高校卒業後、都内の自動車部品会社に就職するが、思い直して青山学院大学文学部英米文学科に進学、25 才で卒業。約10 年間のホテルマン生活を送る。1965 年、作家デビューするも売れない時代が続き、1968 年、ホテル業界を舞台にした小説「銀の虚城」が初めて売れる。1969 年、ホテルを舞台にしたミステリー「高層の死角」で江戸川乱歩賞受賞。1973 年、「腐蝕の構造」で日本推理作家協会賞受賞。「人間の証明」「野性の証明」など映画化・ドラマ化され大ヒットした作品も多い。
山崎豊子
【四十五階のラウンジからは、漆黒の空の下に、宝石をちりばめたようなきらびやかな都心の夜景が広がっていた。】
『新宿・京王プラザホテルの四十五階のラウンジからは、漆黒の空の下に、宝石をちり
ばめたようなきらびやかな都心の夜景が広がっていた。
(中略)
「実はこのホテルがオープンして話題になった頃、弓成さんとタクシーで通りがかった
ことがありますの、一度、行ってみたいですねと何気なく呟いただけですのに、また
今度と面倒くさそうに遮られ、白けてしまいましたわ」
カクテルに唇を近付け、うふっと笑ってみせた。』
文春文庫「運命の人」より
山崎の代表作のひとつ「華麗なる一族」の冒頭の有名なシーン、「陽が傾き、潮が満ちはじめると、志摩半島の英虞湾に華麗な黄昏が訪れる。」の舞台が志摩観光ホテルであることはよく知られているが、山崎自身が毎年、年末年始はこのホテルで過ごしていたのだという。ある時、実際に目にした関西では有名な財閥一族のディナーシーンから構想をふくらませ、金融再編にからめて、上品な表の顔の裏側で、妻妾同居に、祖父と妻の関係への疑惑など、おどろおどろしい上流ファミリーの生態を描いた。
関西では、船場の出であることがわかると人の見る目が変わると言われるが、山崎は船場の老舗昆布屋の娘で、「いとはん」として裕福に育った。子供の頃から夏は六甲山の山腹にあった「六甲オリエンタルホテル」に避暑に行くのという暮らしで、ホテルのちょっとした使い方の描写からもホテル慣れしていることがうかがえる。ファッション・デザイナーの世界の裏のどろどろを描いた初期の作品の「女の勲章」でも、船場育ちの主人公は六甲のホテルをしばしば使う。物語の最後に、恋人の学者と共にポルトガルを旅するシーンでは、ポウサーダなどホテル選びにはこだわりを見せている。
生涯に書いた本の総発行部数4,200 万部という大ベストストセラー作家。ところが、52 年間にわたって山崎の秘書をつとめた秘書の野上孝子氏の「山崎豊子先生の素顔」によると、そんな山崎が、パリ滞在時に「ジョルジュ・サンク」にお茶しに入ろうと誘う野上に、「あそこはジョルジュ・サンクやよ。とんでもないと首を振り」こんな高級ホテルに入るだなんてとんでもないと断られたのだそうだ。着るものについてはずいぶんと贅沢した山崎だが、旅先では食と住(ホテル)についてはとことんケチだったと野上は述懐している。もっとも、単にケチとは違い、しまり屋なのだという。たとえば「ニューヨークでは安全第一を心がけ、一流ホテルに躊躇いもなく宿泊する」というので、おそらくホテルに対する興味やこだわりがそれほどなかったのだろう。
もっとも、新しい小説を書き始めるときは、「資料と原稿用紙を携えて、志摩観光ホテルに滞在」したそうだし、年末年始は夫とともに「志摩観光ホテル」で過ごすのを常としており、「お正月の晩餐は、カクテルドレスにミンクのストールを巻き、胸元や指にはダイヤ、真珠、エメラルドなどの宝石を燦然と煌めかせて、英虞湾を見晴るかすダイニングルームのテーブルに着く」のが常だった。
「沈まぬ太陽」では日本航空、後のJALの経営破綻のきっかけとなる日本航空開発が手がけた海外ホテル買収問題を書いている。作中、「ニューヨークのグランドホテル」として登場するホテルとは「エセックス・ハウス」(現『JW マリオット・エセックス・ハウス・ニューヨーク』)である。
冒頭の抜粋文は、外務省機密漏洩・西山事件を扱った「運命の人」からのもので、裁判の判決文で被告の新聞記者と ”情を交わした”と言われた外務省職員の女性に、新しく開業した新宿のホテルについての会話を通して、被告となった新聞記者男性のオンナ心に疎い無粋さを語らせている。
山崎豊子(1924 〜2013)
● 1924 年大阪府大阪市中央区、船場の生まれで実家は老舗昆布屋。旧制京都女子専門学校(現 京都女子大学)国文学科卒業後、毎日新聞社入社。当時、学芸部に在籍していた作家・井上靖のもとで記者として働く。1957 年、「暖簾」で作家デビュー。1958 年、「花のれん」で直木賞受賞。退職して作家活動に入る。主な著書に「白い巨頭」、「不毛地帯」・「二つの祖国」・「大地の子」の戦争3部作、JALをモデルにした「沈まぬ太陽」など。映画化、テレビドラマ化された作品も多い。